出版社内容情報
戦後という《例外時代》をとらえ直す新しい世界的視点。レーガン=サッチャー革命の評価、経済成長信仰の起原について再考をせまる。
内容説明
戦後ブーム期をとらえ直す、これまでにない経済史。長期的、世界的潮流から、政治の経済的不能を描きだした『ワシントンポスト』紙ベスト経済書。
目次
新しい経済学
魔法の四角形
混沌
揺らぐ信念
大スタグフレーション
ゴールド・ボーイズ
割り当てと愛人と
輸出マシーン
夢の終わり
右への転換
サッチャー
社会主義最後の抵抗
アメリカに昇る朝日
失われた一〇年
新しい世界
著者等紹介
レヴィンソン,マルク[レヴィンソン,マルク] [Levinson,Marc]
エコノミスト、歴史家。専門はビジネスと金融。『エコノミスト』誌の経済学および金融エディターを務めた。ニューヨークの銀行でエコノミストとして勤務した後、外交問題評議会で国際ビジネスのシニア・フェロー
松本裕[マツモトユウ]
翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Francis
14
1950年代・60年代の「高度成長」時代は実は人類史上例のない例外的な時代であり、それ以前、それ以降の「低成長」の方がむしろ当たり前であった、と言う内容。経済学史を振り返ってみると高い経済成長について語った本はあまりないんだよね。経済成長と結び付けられるケインズも本来は需要不足による経済不況から金融・財政政策によりいかに脱出するか、を論じているにすぎないはずだったのだが。ただ、高度成長が例外時代であることが明らかになりつつあることは経済学が本来の意味を取り戻す意味では決してマイナスにはならないと思う。2018/12/04
takao
3
現在の低成長が「平常」経済であり、第二次世界大戦後の高度成長期こそが「例外」2022/10/06
Mealla0v0
3
戦後経済史を1945-73までの高度成長期と、オイルショック以降の低成長期に分けるとすると、前者は「例外時代」(直訳すれば「異常な時代」)と呼ぶことのできる時代である。その理由は戦争からの復興に加え、エネルギー効率のよい石油の使用にある。経済成長はいつまでも続くと思われ、この成長を前提とした制度設計が行われ福祉国家が誕生する。公共事業や社会保障といったものは成長期には歓迎されたが、成長の鈍化によって批判の対象へと転落した。オイルショックが新自由主義の台頭を招いたものの、成長は取り戻せないままでいる。2022/05/02
ミッキー
3
生産性向上の為に未利用労働力を活用した戦後。今まで経済学を学んで来たことが色褪せて思える。蛮勇を奮い立たせることが成長に繋がるのだと少し切なく思う。学ぶべきことがまだまだあります。2018/07/16
Go Extreme
1
好転していた経済のインフレーション 労働者の賃金を守るためのデモ行進 安定はあくまで例外 需要牽引型インフレ コストプッシュ型インフレ 望ましくないが避けられない厄介者 インフレ しつこいインフレと経済的停滞 スタグフレーション 税金は労働意欲を弱体化 福祉国家のコスト増大と財源問題 規制撤廃 イノベーションの波 強力だった炭鉱労働組合の征服 銀行業務の国際化とリスク増大 輸出マシーンと呼ばれた日本 石油危機 日本への警鐘 生産性向上の驚異的な速度 生活水準向上と福祉国家拡大の財源 安定が手の届かない贅沢2025/05/21
-
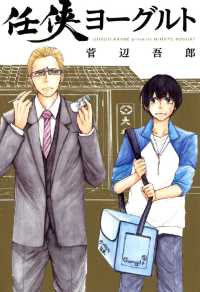
- 電子書籍
- 任侠ヨーグルト uvu
-
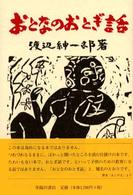
- 和書
- おとなのおとぎ話







