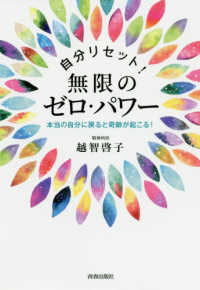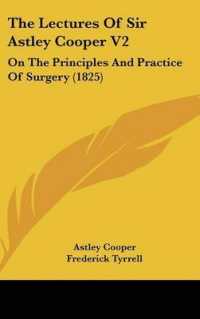出版社内容情報
半世紀にわたり読みつがれてきた社会学の名著を改訂訳で。上巻は第一部「性格」。著者が初版から20年後に執筆した新たな序文を付す
半世紀にわたり読みつがれてきた社会学の名著を改訂訳で。上巻は第一部「性格」。著者が初版から20年後に執筆した新たな序文を付す
内容説明
「社会の諸制度が個人のなかに、その社会にふさわしい性格をうえつけてゆく」。個人と社会、時代との関わりを論じた不朽の名著、改訂訳版で登場。初版(1950年)から20年後に書かれた新たな「まえがき」を付す。
目次
第1部 性格(性格と社会のいくつかのかたち;道徳性から意欲へ―誰が性格形成をしてきたか;仲間たちの審判―誰が性格形成をしてきたか(つづき)
物語技術のさまざま―誰が性格形成をしてきたか(つづき)
内部指向の生き方
他人指向の生き方―「神のみちびき」から「お愛想」へ
他人指向の生き方(つづき)―もうひとつの顔)
著者等紹介
リースマン,デイヴィッド[リースマン,デイヴィッド][Riesman,David]
1909年フィラデルフィアに生まれる。最初ハーバード大学で生化学を専攻、つづいて法学部に学び、弁護士としてアメリカ最高裁判所判事ルイス・ブランダイスの秘書をつとめる。そのかたわら、法律学の教師や実務を経て戦後、学界に入る。1949年シカゴ大学教授、1958年以後、ハーバード大学社会科学教授、同名誉教授。2002年没
加藤秀俊[カトウヒデトシ]
1930年(昭和5年)東京に生まれる。東京商科大学(現・一橋大学)卒業。京都大学人文科学研究所助手、京都大学教育学部助教授、ハワイ大学東西文化センター研究員、学習院大学教授、中部高等学術研究所所長、国立放送教育開発センター所長、国際交流基金日本語国際センター所長、日本育英会会長などを歴任。中部大学学術顧問。社会学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ざっく
イボンヌ
ぽん教授(非実在系)
ヨンデル
ポルターガイスト