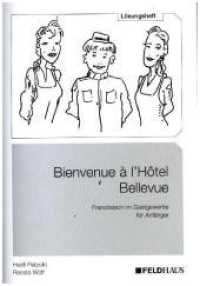出版社内容情報
***
1930年代から十数年の間に発表されたアランの芸術・文芸批評。自己の思惟は他者の思惟によって培われることを知り抜いていたアランは、すぐれた読者であり、同時に子どものように純粋に読むことの愉しみを知る、最上の読者だった。ラブレー、バルザック、ヴァレリー… アランの愛したこれら作家たちの人と作品が語られ、また、画家アングルが、バッハやセザール・フランクの音楽が解き明かされる。
要約や抜粋、解説や註釈とはいっさい無縁、作品の前に心を開き、おのれ自身と共鳴するものを受け入れてはじめて、種子は蒔かれ、古典は再生産されてゆく――読者自身の思索を誘い出そうとするアラン一流の論説、全10篇。
内容説明
表現形式や技法に包容された作品の生命を己の内に吸い込む。そして導かれる思索。衒学に傾く同時代の批評に対して生まれた、感嘆と歓びに満ちた芸術批評。
目次
ラブレー
サン=シモン
野心のロマネスク―あるいはスタンダール流の恋愛について
バルザックの文体
詩人の立場―ヴィクトル・ユゴーを讚える
ラペルーズでの午餐
詩を讃える
アングル―あるいはデッサンと色彩の対立
ヨハン=セバスチャン・バッハの言語
セザール・フランク
著者等紹介
アラン[アラン][Alain]
1868‐1951。本名・Emile Auguste Chartier。ノルマンディーに生れ、ミシュレのリセ時代に哲学者J・ラニョーの講義を通して、スピノザ、プラトン、デカルト、カント、ヘーゲル等を学ぶ。エコール・ノルマル卒業後ルーアン、アンリ4世校等のリセで65歳まで教育に携る。ルーアン時代に「ラ・デペーシュ・ド・ルーアン」紙に「日曜日のプロポ」を書きはじめたのが彼のプロポ(語録)形式の初めである
山崎庸一郎[ヤマザキヨウイチロウ]
1929年生。1953年東京大学文学部仏文科卒業。2000年3月まで学習院大学文学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
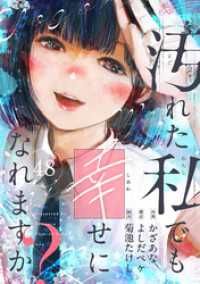
- 電子書籍
- 汚れた私でも幸せになれますか?(48)…