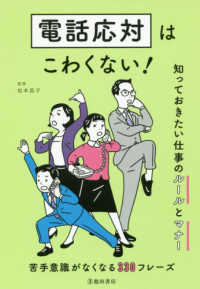内容説明
精神医学と宗教は、どのような関係を持ちうるのであろうか。無意識が内在する宗教性を、人間の実存を解明する鍵として考察し、精神療法への応用を志向する。講演集「ロゴスと実存」を併収。
目次
実存分析の本質
精神的無意識
良心の実存分析
実存分析的な無解釈
良心の超越
無意識の宗教性
精神療法と宗教〔ほか〕
著者等紹介
フランクル,V.E.[フランクル,V.E.][Frankl,Viktor Emil]
1905年、ウィーンに生れる。ウィーン大学卒業。在学中よりアドラー、フロイトに師事し、精神医学を学ぶ。第二次世界大戦中、ナチスにより強制収容所に送られた体験を、戦後まもなく『夜と霧』に記す。1955年からウィーン大学教授。人間が存在することの意味への意志を重視し、心理療法に活かすという、実存分析やロゴテラピーと称される独自の理論を展開する。1997年9月没
佐野利勝[サノトシカツ]
1918年大阪府に生れる。1941年京都帝国大学経済学部卒業。1946年京都大学文学部卒業。京都大学・滋賀医科大学名誉教授
木村敏[キムラビン]
1931年外地に生れる。1955年京都大学医学部卒業。現在、京都大学名誉教授。河合文化教育研究所主任研究員。精神病理学専攻
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
赤
0
フランクルの基本的な思想は、人は心と区別された精神を持つものであり、その実存を重視するべきであるといったものであるが、本書はその論を深く掘り下げ、無意識における精神、実存分析的な夢解釈など非常に面白い考察がなされている。心理と精神の区別が無意識にも及んでいるというのは原理的にも十分納得がいくのだが、その夢解釈においては曖昧な印象を受けた。夢解釈が具体的になされているが、実際どのようにでも解釈でき、それが精神的な象徴なのか、それとも心理的なものなのか、判別はとても難しいように思われる。2014/09/16
アマゾン光介
0
無神論者が無意識下では、つねに神を志向しているというフランクルの主張。 ー「私たちは、たとえ無意識にであれ、つねに既に神を志向している」 (『識られざる神』)ー ニーチェも、その例外ではなかったようだ。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1525004676/18 そして、ヘルダーリンの珠玉の言葉を、この書で知った。 「自らの不幸に直面するとき、私は一段高いところに立つ」(『識られざる神』 P.131)