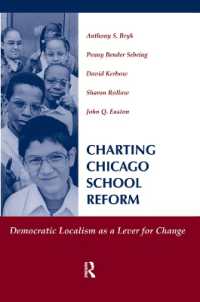出版社内容情報
今日のコミュニティ論におけるキーワード「サードプレイス」。その社会学的概念と意義を論述し、広く一般に知らしめた本の待望の邦訳
今日のコミュニティ論におけるキーワード「サードプレイス(第三の場)」。第一の場=家、第二の場=職場・学校の中間的位置にあり、そこでは役割を持たない匿名の人としてもふるまえて、くつろげる場所のこと。具体的には、町の飲食店だ。この概念の社会学的意義を論述し、広く一般の人々の賛同を集めた著書の待望の邦訳。解説は、マイク・モラスキー氏。
はしがき
第二版へのはしがき
謝辞
序論
第?T部
第1章 アメリカにおける場所の問題
第2章 サードプレイスの特徴
第3章 個人が受ける恩恵
第4章 もっと良いこと
第?U部
第5章 ドイツ系アメリカ人のラガービール園
第6章 メインストリート
第7章 イギリスのパブ
第8章 フランスのカフェ
第9章 アメリカの居酒屋
第10章 古典的なコーヒーハウス
第?V部
第11章 厳しい環境
第12章 男女とサードプレイス
第13章 若者を締め出すということ
第14章 めざすは、よりよい時代……と場所
解説(マイク・モラスキー)
註
参考文献
索引
内容説明
居酒屋、カフェ、本屋、図書館…情報・意見交換の場、地域活動の拠点として機能する“サードプレイス”の概念を社会学の知見から多角的に論じた書、待望の邦訳。
目次
第1部(アメリカにおける場所の問題;サードプレイスの特徴;個人が受ける恩恵;もっと良いこと)
第2部(ドイツ系アメリカ人のラガービール園;メインストリート;イギリスのパブ;フランスのカフェ;アメリカの居酒屋;古典的なコーヒーハウス)
第3部(厳しい環境;男女とサードプレイス;若者を締め出すということ;めざすは、よりよい時代…と場所)
著者等紹介
オルデンバーグ,レイ[オルデンバーグ,レイ] [Oldenburg,Ray]
1932年生まれ。アメリカの都市社会学者。西フロリダ大学社会学部名誉教授。州立マンカト大学(現・ミネソタ州立大学マンカト校)で英語と社会科の学士号、ミネソタ大学で社会学の修士号および博士号を取得。ネヴァダ大学、州立スタウト大学(現・ウィスコンシン州立大学スタウト校)、ミネソタ大学を経て1971年から2001年まで西フロリダ大学で教鞭をとる。過去には小学校・中学・高校の教諭や米国陸軍医療部隊の歯科技工士として働いた経験もある。“サードプレイス”づくりに取り組む国内外の行政や企業、市民のコンサルタントとしても活躍
忠平美幸[タダヒラミユキ] [Molasky,Michael]
1962年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。早稲田大学図書館司書を経て現在は翻訳者
モラスキー,マイク[モラスキー,マイク]
1956年アメリカ・セントルイス生まれ。シカゴ大学大学院東アジア言語文明研究科博士課程修了(日本文学)。学術博士。専攻は戦後日本文化史。ミネソタ大学アジア言語文学部教授、一橋大学社会学研究科教授を経て、2013年9月より早稲田大学国際学術院教授。日本の戦後文化、ジャズやブルースを中心とする音楽文化論、東京論、そして喫茶店や居酒屋のような都市空間をテーマに研究活動を行う。著書に、『戦後日本のジャズ文化』(青土社、2005/サントリー学芸賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おさむ
katoyann
Nobuko Hashimoto
スイ
gecko
-

- 電子書籍
- たぶん悪役貴族の俺が、天寿をまっとうす…