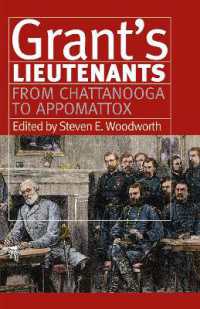出版社内容情報
20年にわたって書き継がれた音楽批評の初の集成。サイードのもうひとつのライフワーク。
全2巻
内容説明
2巻はバッハ、ベートーヴェン、ヴァーグナー、ブーレーズほか重厚な作家作品論を中心に死の直前までの10年分を収録。刮目すべき未完の書の起草文を巻末に付す。
目次
第2部 一九九〇年代(承前)(バード音楽祭;ヴァーグナーに対しては不忠実であるほうが忠実である;身ぶりの音楽―ショルティについて;ベルリオーズ『トロイアの人びと』 ほか)
第3部 二〇〇〇年代(文化の壁を越えた絆―ダニエル・バレンボイム;グレン・グールド知識人であった巨匠;宇宙的な野心―クリストフ・ヴォルフ著『ヨハン・ゼバスティアン・バッハ』;バレンボイムとヴァーグナーの禁忌 ほか)
著者等紹介
サイード,エドワード・W.[サイード,エドワードW.][Said,Edward W.]
1935年11月1日、イギリス委任統治下のエルサレムに生まれる。カイロのヴィクトリア・カレッジ等で教育を受けたあと合衆国に渡り、プリンストン大学卒業、ハーヴァード大学で学位を取得。コロンビア大学英文学・比較文学教授を長年つとめた。2003年9月歿
二木麻里[フタキマリ]
1960年生まれ。上智大学外国語学部卒、東京大学大学院学際情報学府博士課程在。和光大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
11
モーツァルトは音楽の内外双方で自由を探究したという(72頁)。コンサートを開くことは奏者にとって強烈な競争社会に投げ込まれることを意味する(130頁)。読書会を開くことは生涯学習のお役に立つことで、自らの所得補てんというだけだが。競争の格差というのも問題である。師匠というか、巨匠という存在がヨーロッパの音楽界に独立勢力として現れたのはパガニーニやリスト以降(211頁)。私には音楽史の知識を持ち合わせていないのでこれから勉強。グールドの講演(1964年)で、「創造的な着想は発見の継続」(218頁)とのこと。2014/01/20
takao
2
☆思想と同じように音楽においても小さな細部が調和し、大きな視野が生まれる。2018/02/18
ゆるこ
2
「サイードの文体はひどく難解なのに、楽曲が語られる箇所では不思議なほど鮮やかに脳裏で音が鳴った。音楽家の文章であった」と、訳者のあとがきの最後に書いてあった。本当にそうだったな。理解できないところもたくさんあったけど、愉しかった。バッハについての文章、グールドについての文章、バレンボイムについての文章は特に。思わず息が荒くなったり涙が出そうになったり笑っちゃったりして、電車の中で読んでたから、はたから見たら怪しさ満開だったに違いない。 またしばらくしてもう一度読みたい。もう少し理解したいからね。2014/03/08
夢仙人
1
素晴らしい。老後、じっくりと読もう。2017/06/11