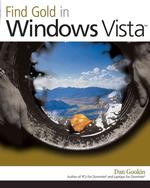- ホーム
- > 和書
- > 文芸
- > 海外文学
- > その他ヨーロッパ文学
内容説明
15歳の少年が経験したアウシュヴィッツを静かに崇高に綴った自伝的小説。死の淵から“人間性”“信仰”“愛”とは何かを問いかける永遠の古典を改訳でおくる。
著者等紹介
ヴィーゼル,エリ[ヴィーゼル,エリ][Wiesel,Elie]
1928年トランシルヴァニアの小都市シゲットに生まれたユダヤ人作家。1944年アウシュヴィッツの強制収容所に入れられ、翌年ブーヘンヴァルトの強制収容所で解放を迎える。帰郷を拒んでパリのソルボンヌ大学に学ぶ。のちに新聞記者となり、1956年に渡米して市民権を得る。1986年ノーベル平和賞受賞。現在ボストンに住み、フランス語で文筆活動を続ける
村上光彦[ムラカミミツヒコ]
1929年佐世保に生まれる。1953年東京大学文学部仏文学科卒業。現在、成蹊大学名誉教授、大佛次郎研究会会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
chimako
81
ノーベル文学賞作家のドキュメンタリー。自分の経験を客観的に、装飾せず、日記のように書き記す。トランシルヴァニアの小さな町からゲットーへ。そして悪魔の住む地獄のアウシュヴィッツへ。神がいるのなら何故このような仕打ちをなさるのか。祈るの事をやめ、感じることをやめ、愛することさえもやめてしまいたくなる。別々になった母や妹を忘れ、弱った父親を足手まといと思う自分を恥じながら、それでも父の最期を看取ろうとする。父は死にその後1ヶ月半ほどで自由の身となる。極限で人は何を思うのか。何をするのか。厳しい読書だった。2020/07/23
syaori
71
本書で一番恐ろしかったのは、凄絶な強制収容所体験よりも、主人公の住む町の人々が戦争やシオニズムに関心を寄せながら、前兆や不安に蓋をして「もう遅すぎる」ところまで行ってしまうことでした。彼らは言う「ドイツ軍はここまで来はしないさ」「二十世紀のさなかに」1民族を皆殺しにするなんて。そうして彼らはアウシュヴィッツへ行き着くのだ。でも私たちも世界もいつだって、気付いたときには「遅すぎる」ところにいるのだと思います。まだ大丈夫、自分は大丈夫だと思いながら。だからこそ、この怖さを忘れないようにしたいと思いました。2020/09/02
こばまり
58
描かれた内容の非情さは勿論のこと、内省的で文学性に富んだ文体の為か、読みながら度々茫然となる。ある日突然ではなくじわじわと確実に全てを剥奪されていく様が心底恐ろしい。本書を手に取り帰宅後、作者死去の報に接する奇遇。2016/07/08
breguet4194q
55
ノーベル平和賞授賞者の自伝です。ホロコーストに関する部類の中では、生々しい描写は比較的少ないと思います。ただ、著者は衰弱し死に至る父親に対する自分の心理を、冷静書いてます。極限状態において、自分以外の事に傍観的になり、更に父が死亡した時にはもう面倒みなくていいという開放感。ここまで正直に書く勇気って、本当に偉いと思いました。2021/08/29
みねたか@
23
「夜と霧」、「アウシュヴィッツは終わらない」に続いて手に取った強制収容所での体験が記された作品。人生を大きく変えてしまった収容所での第一夜、迫るソ連軍から逃れる強制収容所間の過酷な移動など、収容所での凄絶な体験はもちろん強く迫るものがある。だが、本書で最も印象深いのは、ファシストが政権につきゲットーに押し込めらてもなお人々はいずれ何もかも元に戻ると楽観視していたということ。正常性バイアスとは恐ろしい。自分の現実認識も自信がなくなってくる。2024/09/30
-

- 電子書籍
- 大富豪の秘密の婚約者【分冊】 7巻 ハ…