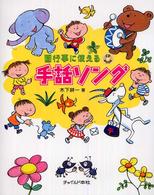内容説明
人が外傷と自己の存在との闘いのなかで表す病、解離性障害…そしてトラウマ、虐待、自傷、倒錯、絶望。ひとりの精神分析臨床家がこころの真実に挑んだ。
目次
解離性障害治療私史
第1部 解離性障害を理解するために(総説―解離の理解と治療論;外傷と境界性パーソナリティ障害、そして、解離性同一性障害)
第2部 ある解離性同一性障害患者との心理療法(心的外傷の再演としての治療外転移解釈;性的外傷、性倒錯、そして解離;心的外傷の再演の臨床的取り扱い)
第3部 解離性障害をめぐる臨床上の諸問題(思春期解離性同一性障害患者の治療―心理療法、マネージメント、そして「抱えること」;離人症性障害の心理療法―患者によりあらかじめ期限が設定された心理療法;解離性障害と自傷;一般精神科臨床における解離性障害の治療に関する覚書)
著者等紹介
細澤仁[ホソザワジン]
1963年に生まれる。精神科医。臨床心理士。1988年京都大学文学部卒。1995年神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学系研究科助手、神戸大学保健管理センター助手、兵庫教育大学大学院学校教育研究科講師を経て、兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授・同大学保健管理センター所長。日本精神分析学会認定精神療法医ならびに認定精神療法医スーパーバイザー。日本精神神経学会精神科専門医。2005年度日本精神分析学会学会奨励賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みそ
2
転移の扱いや退行の考え方、勉強になることばかり。普段意識できていないことに気づかされて痛いところをつかれたように思う。治療同盟を結んで構造化することにより不必要な退行を避けること、受容と共感が危険となる場合、自我機能をアセスメントする大切さ、錯覚と脱錯覚により対象を現実的に感じられるようにすること、違う心をもつ別の人間として存在すること。転移を扱えるようになるには普段から自分の状態に思いをめぐらせて、特にしんどい状態になった時に自分はどうなるのか考えられるようになることが大事だなあと思う。2020/08/22
nickcave
1
この著者は解離というか、人間のこころの情動を根本的に理解できていないのではないかと思われる。著者の解離患者に、他の精神科医では考えられないほどの尋常ならざる激しい行動化、退行が表れるはそのためだろう。また、患者のこの症状を転移・逆転移の関係に求めすぎている。この「私が、私に」というおおよそ医師にあらざるべき姿勢は、著者が精神科医として不適格な人格であると断ざるをえない。2015/12/22
tuna
1
精神分析理論による解離の治療論。こんなに積極的に転移解釈するのかと驚いた。取りあえず真似はできそうにない。事例は困難なケースが多く、転移解釈が目立つ一方で、ホールディングが本質的な意味を持っていることが理解できる。精神分析における「解離」の位置づけ、「抑圧」と「解離」の異同なども整理されている。2014/02/21