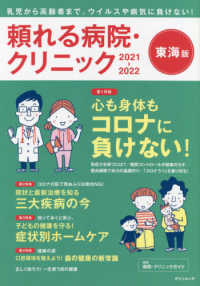出版社内容情報
***
エドワード・O・ウィルソンの大著『社会生物学』(1975)はたちまち非難の嵐を巻き起こした。とりわけ動物行動の研究を人間社会に適用すると明言したその最終章をめぐって、社会の現状維持を正当化し人種差別を肯定する悪しき遺伝子決定論であるとの批判が向けられたのである。
論争はイギリスにも飛び火し、やがてドーキンスとグールドは、やや論点をずらしながら、大洋をはさんで果てしなく思われる応酬をくり広げていく。だが、四半世紀をへて、社会生物学は一方でたとえば進化心理学のような学問分野を生み、また論議の焦点のいくらかはサイエンス・ウォーズやヒューマン・ゲノム・プロジェクトのほうへ移り、等々、社会生物学論争は、少なくともほぼ、終幕を迎えているといっていい。あの仮借ない戦いは、何だったのか。
著者セーゲルストローレが科学社会学者としてインタヴューする相手は、グールド、ドーキンス、メイナード・スミス、ハミルトン、メダワー、ルリア……もちろん〈首魁〉ウィルソンとルウォンティンをはじめ、論争の立役者のほぼすべてからゴシップも含む得がたい証言をあつめ、そこにきわめてバランスのとれた迫真の考察を加え、セーゲルストローレは論争の顛末を一気に語りおろす。社会生物学論争に言及するとき、本書を避けて通ることはできない。
全2巻
ウリカ・セーゲルストローレ(Ullica Segerstrale)
フィンランドに生まれ育つ。ヘルシンキ大学で有機化学・生化学を修めた後、科学社会学に専攻を転じ、1983年にハーヴァード大学でPh.D.取得。現在、イリノイ工科大学社会学教授、社会科学部主任教授。シカゴ在住。おもな編著にBeyond the Science Wars: The Missing Discourse about Science and Society (State University of New York Press, 1999), Nonverbal Communication: Where Nature Meets Culture (ed. with Peter Molnar, Lawrence Erlbaum Associates, 1997)ほかがある。
垂水雄二(たるみ・ゆうじ)
1942年大阪に生まれる。京都大学大学院理学研究科博士課程修了。出版社勤務をへて1999年よりフリージャーナリスト。著書『やぶにらみ生物学』(ACORN、1985)ほか。訳書 ブロイアー『社会生物学論争』(どうぶつ社、1988)、ドーキンス『利己的な遺伝子』(共訳、紀伊國屋書店、1991)『遺伝子の川』(草思社、1995)『悪魔に仕える牧師』(早川書房、2004)、アーリック『トンデモ科学の見破りかた』(共訳、草思社、2004)、ハンフリー『喪失と獲得』(紀伊國屋書店、2004)ほか多数。
内容説明
“首魁”ウィルソンとルウォンテイン、グールド、ドーキンス、メイナード・スミス、メダワー、ルリア…主な関係者すべてのインタヴューをもとに科学社会学者が語りおろす社会生物学論争の顛末。
目次
真理をめぐる闘いとしての社会生物学論争
第1部 社会生物学論争で何があったのか(社会生物学をめぐる嵐;衝突に突き進む同僚―ウィルソンとルウォンティンの正反対の道徳的かつ科学的課題;英国派とのつながり;社会生物学の秘められた背景;適応主義への猛攻―遅ればせの科学的批判;淘汰の単位と、文化との関連;批判に適応する社会生物学―『遺伝子・心・文化』;道徳的/政治的対立はつづく)
著者等紹介
セーゲルストローレ,ウリカ[セーゲルストローレ,ウリカ][Segerstrale,Ullica]
フィンランドに生まれ育つ。ヘルシンキ大学で有機化学・生化学を修めた後、科学社会学に専攻を転じ、1983年にハーヴァード大学でPh.D.を取得する。イリノイ工科大学社会学教授、社会科学科主任教授。シカゴ在住
垂水雄二[タルミユウジ]
1942年大阪に生まれる。京都大学大学院理学研究科博士課程修了。出版社勤務をへて1999年よりフリージャーナリスト
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
kenitirokikuti
Ryosukem90
Ryosuke Tanaka
山像
-

- 電子書籍
- サーシャちゃんとクラスメイトオタクくん…
-

- 電子書籍
- 公器の幻影 小学館文庫