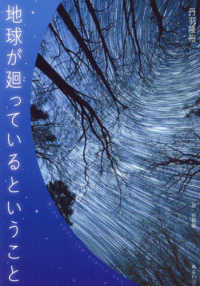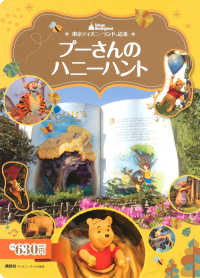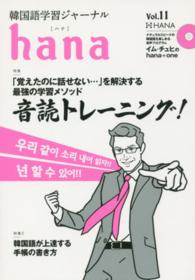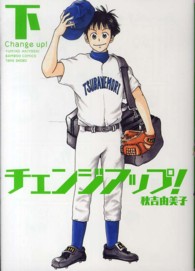出版社内容情報
マルクス主義革命の要請、キューバ革命、新中国の誕生など、政治的問題の数々から芸術運動上の革新、民族学、精神分析などの知的冒険に到るまで、二十世紀のさまざまな運動に巻き込まれ、これと向き合い、場合によっては自殺未遂行為に及ぶほどに自分自身を陰鬱な精神状態に追い込んで書かれなければならなかった記録がここにある。 これはレリスにとっての「書物」もしくは「書物の鏡」というべきものである。文章上の彫琢がなされた完成品ではない。未完成というよりも、そもそも完成などあるべくもない、しかもトータルな何かを志向する身振りからなるテクスト空間、すなわち「幻の書物=書物の幻」そのものが物質化した姿がここにある。 この『日記』がわれわれにとって貴重なのは、まさに状況に巻き込まれ、いわば見通しのよさなど望むべくもない悪天候のなかで低空飛行をつづけながら、執拗に書きつづけたというその一点にある。ここにあるのは、二度の大戦に見舞われたヨーロッパに生きたひとりの人間の等身大の姿、地上1メートル何十センチかの高さにある視点なのだ。
Michel Leiris(ミシェル・レリス)
1901年、パリ生まれ。作家・民族学者。1920年代にシュルレアリスム運動に加わり、その後ダカール=ジブチ調査旅行(1931‐33)を経て民族誌研究の道に進み、人類博物館に勤務。自伝的作品として『成熟の年齢』および『ゲームの規則』全4巻があリ、民族誌の分野ではとくに憑依現象に関する著作を残す。1990年没。ほかに邦訳として『黒人アフリカの美術』(新潮社、1968)、『ミシェル・レリスの作品』(全4巻、思潮社、1970‐72)、『夜なき夜 昼なき昼』(現代思潮社、1970)、『闘牛鑑』(現代思潮社,1971),『幻のアフリカ』(河出書房新社,1995)、『オランピアの頸のリボン』(人文書院、1999)、『ピカソ・ジャコメッティ・ベイコン』(人文書院、1999)などがある。
Jean Jamin(ジャン・ジャマン)校注
パリ社会科学高等研究所。人類学者。人類博物館勤務を経て、現在コレージュ・ド・フランス社会人類学研究室に勤務し、研究誌L'Hommeの編集にあたる。またミシェル・レリスの遺言執行人として、彼の死後、精力的に遺稿の出版にあたる。著書にAux origines de l'anthropologie francaise, La Sycomore, 1978; Jean-Michel Place, 1994がある。
千葉文夫(ちば・ふみお)訳
1949年北海道生れ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程中退。現在 早稲田大学文学部教授。フランス文学。著書『ファントマ幻想』(青土社)。訳書にレリス『角笛と叫び』(青土社)、クロソフスキー『ローマの貴婦人』(哲学書房)、シュネデール『グレン・グールド 孤独のアリア』(筑摩書房)、シュネデール『シューマン 黄昏のアリア』(筑摩書房)、『プーランクは語る』(筑摩書房)、マセ『最後のエジプト人』(白水社)、ドゥレ『リッチ&ライト』(みすず書房)など。
感想・レビュー
-

- 和書
- ファシリテーターになろう