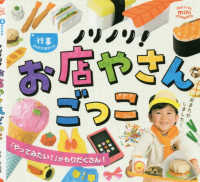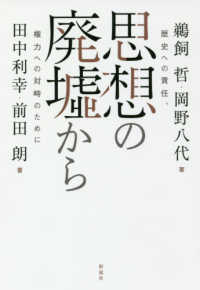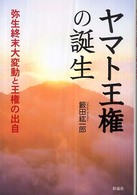出版社内容情報
ホメロスからボルヘスまで、この作家一流の読み方で作品と作者を語る、とびきりの世界文学案内。
「『不在の騎士』や『見えない都市』など、明晰でリズム感にみちた文体と、ゆたかな寓意性にいろどられた一連の物語の作者として20世紀後半の世界に名を馳せたイタロ・カルヴィーノは、また、戦中・戦後のイタリア文化の輝かしい担い手であったエイナウディ出版社を代表する編集社のひとりとしても、傑出した存在だった。ここに集められた文章の多くは、同社の文学叢書の「まえがき」として書かれたものだ」(訳者あとがきより)
ディケンズのなかにベケットを発見し、バルザックとベンヤミン、スタンダールとロラン・バルトの絆を認めて、心を躍らせながら、カルヴィーノのことを、いま惜しむのである。
内容説明
ぎっしり三十篇のエッセーを収めた本書は、文学を読む愉しみにあらためて気づかせてくれる。
目次
なぜ古典を読むのか
オデュッセイアのなかのオデュッセイア
クセノポン『アナバシス』
オウィディウスと普遍的なつながり
天、人間、ゾウ
『狂乱のオルランド』の構造
八行詩節の小さなアンソロジー
ガリレオの「自然は書物である」〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
U
35
須賀敦子さんの訳というのに惹かれ、武満徹氏も愛した、イタロ・カルヴィーノによる文学論を手にとった。一章一章が短く気ままによめる。今回この本でであったフランシス・ポンジュに興味津々。2016/03/13
Ecriture
18
なぜ古典を読むのかについて300ページ書いてるわけではない(実際は最初の10ページ程度しか古典論はない)のでご注意を。古典とは、「今読んでいるところ」とは言わずに「今読み返しているところ」と人が言うような書物。これホント。初めて読むときも実は読み返しているもの。これもホント。ナボコフ流の「読書には再読しかない」には自分擁護の腹立たしさがあるが、カルヴィーノ流の再読論には納得。「なぜ古典を読むのか」と問う以前に「既に読んでしまっている」ものが「古典」の名を有する。たとえ本に触れたことがなくとも。2012/06/27
rabbitrun
5
書名と訳者を見て読んだものの難解だった。が、冒頭の古典の定義は面白い。2014/12/27
viola
3
これは題名がおかしい!古典文学に惹かれる理由を延々と語っているのかと思いきや・・・本当に寄せ集め。しかも、文豪の作品でもマイナーなものを中心に取り上げているので、さっぱり分からない。第1章だけかな。2009/03/11
ちょろいも
2
タイトルから想像する内容ではなかったけれど、有意義な読書でした♪2008/08/05