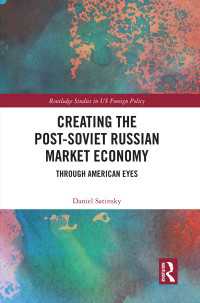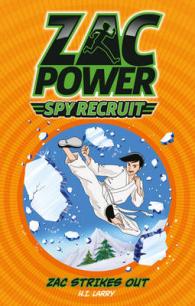- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 芸術・美術一般
- > 芸術・美術一般その他
出版社内容情報
鮮やかな余白を求めて国際的に活躍する美術家が自身の芸術、作家たち、ものと言葉について綴る。
カンバスの上に一つの点を打つと、辺りの空気が動き出す。一筆のストローク、一個の石、一枚の鉄板は、外との対応において力に漲る生きものとなり、物や空間が呼応し合って、鮮やかに響きわたる余白が生まれる――1970年代、有機的な組替えやズラしによって、外の空気を浸透させ他を受け入れる作品を精力的につくり、あるがままをアルガママにする仕事をした「モノ派」、その運動の柱として知られ、国際的に活躍する李禹煥の著作を集める。
自身の芸術について、セザンヌやマチスに始まり、ゲルハルト・リヒター、ペノーネ、若林奮、白南準ら現代芸術の旗手たち、古井由吉や中上健次などの作家たちについて、そして、ものと言葉について…
自分と、自分をとりまく外の世界。その境界にあたらしい刺激的な見方を開く。
受賞情報:
第13回 高松宮殿下記念世界文化賞を著者李禹煥さんが受賞
書評情報:
松山 巌さん/朝日新聞 2001.2.4)
李禹煥(リ ウファン)
美術家。1936年、韓国慶南地方に生まれる。文人として知られた黄東蕉から幼年期を通して詩・書・画を教わる。1956年、ソウル大学校美術大学を中退し、来日。1961年、日本大学文学部卒業。1967年、東京・サトウ画廊にて新しい試みの最初の個展、以後、前衛的な芸術表現を追求しながら国際的に活躍。1968年頃から起こった「もの派」運動の柱として知られ、パリ・ビエンナーレ、カッセル・ドクメンタ他多くの国際展に出品、デュッセルドルフ・クンストハーレ、パリ・ジュ・ド・ポム美術館、神奈川県立近代美術館をはじめ、国内外の美術館などで個展。前パリ国立エコール・ド・ボザール招聘教授。現在、多摩美術大学客員教授。
作品集『LEE UFAN』(1986,美術出版社),『LEE UFAN』(1993,都市出版),『李禹煥全版画 1970-1998』(1998,中央公論美術出版)ほか。著書『時の震え』(1988,小沢書店),『出会いを求めて』(1971, 田畑書店 2000,美術出版社),“Selected Writings by Lee Ufan 1970-1996”(1996,Lisson Gallery, London)
内容説明
1970年代、有機的な組替えやズラしによって、外の空気を浸透させ他を受け入れる作品を精力的につくり、あるがままをアルガママにする仕事をした「モノ派」、その運動の柱として知られ、国際的に活躍する李禹煥の著作を集める。そして著者自身の芸術について、セザンヌやマチスに始まり、ゲルハルト・リヒター、ペノーネ、若林奮、白南準ら現代芸術の旗手たち、古井由吉や中上健次などの作家たちについて、そして、ものと言葉について…自分と、自分をとりまく外の世界。その境界にあたらしい刺激的な見方を開く。
目次
余白の芸術
さまざまな作家
芸術の領分
新しい表現の場のために
ものと言葉について
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
A.T
Nepenthes
Yoshi
ルートビッチ先輩
のんたんの