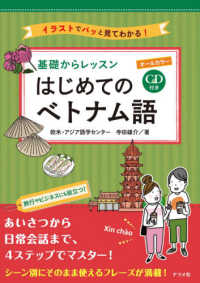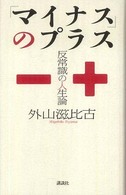出版社内容情報
15-18世紀の全世界にわたる衣食住の様相を描く。小麦・稲・とうもろこし等の人間集団への影響。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うた
7
歴史は無数の挿話から成っている。人口、食べ物、飲み物、服、住居の話が延々と続くのだが、意外と面白く読めた。小麦や米の生産性、欧州における肉の位置付け、疫病の人口への影響。各地の生活風景や経済状況がゆっくりと立ち上がってくる。どれだけ調べれば、こんなとんでもないものが書けるのやら。2014/11/16
うえ
5
「その昔、16世紀にいたるまで(そののちまでも)じつに珍しい慣わしがあった…一階や寝室の嵌木床に、冬は藁を敷き、夏は青草や花を敷いたのである…王宮にも同じ慣わしがあった。1549年6月、パリ市がカトリーヌ・ド・メディシスのために催した宴会のさいに、心をこめて<広間に上等の匂い草が撒き散らされ>た…なおこれらの花・草・葦は、取り替えなくてはならなかった。ところが、エラスムスの語っているところによると、イギリスではかならずしも取り替えが行われなかった。そのために汚物や屑がおのずから床に積み重なっていった」2017/03/02
roughfractus02
4
資料を所有する側の権威を強化してきた単線的歴史は、それ以外を資料として扱う余地を与えず、権威が管理する事件資料による政治史を優先する。著者率いるアナール学派は、この権威に対して事件より構造を重視すると宣言する。著者は時間を長期(持続)・中期(重合)・短期(事件)に区分し、従来の歴史を短期の層に位置付け、気候や環境の変動、日常生活での食習慣、技術を長期の変動から本書を始める。中期、短期は物理学の隷属原理さながら長期に影響されるが、短期が長期に組み込まれる逆行も想定する。著者はその舞台となる中期を構造と呼ぶ。2020/06/04
月世界旅行したい
3
おすすめ。2014/04/17
もみち
2
【大学】173ページまで読了。2017/04/11