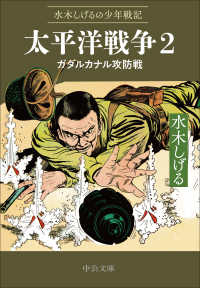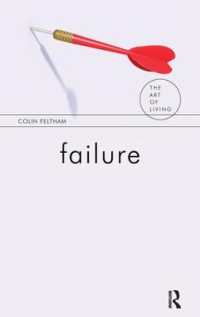内容説明
本書は1932年に刊行された。これはワイマール共和国の崩壊前夜、翌年にはヒトラーが政権を掌握する時機にあたる。左右対立による政治の混迷、ファシズムの台頭と経済危機、教養の解体と文化への憎悪、このような状況の中で、クルツィウスはドイツの民族と文化、ひいてはヨーロッパ文化について熟考し、その未来を展望している。
目次
1 教養の解体と文化への憎悪
2 国民か革命か?
3 大学の危機
4 社会学か革命か?
5 イニシエーションとしての人文主義
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
LM
1
【通読】1932年のナチス前夜のヴァイマル共和国で書かれた本。大学における学問分野の細分化を戒め、「教養」を得るためにはひとつの専門知を学ぶだけでは足りないとした上で、人文主義の復興を主張する。今日において「ナショナリズム」と称されるような神話を新たに作るのではなく、ローマ以来の伝統をそのまま受け止めた伝統を構想するのは、時代背景とともに考えると興味深い。ただ、第4章におけるマンハイム批判はわからなかったので、どこかで秋元律郎『マンハイム:亡命知識人の思想』(ミネルヴァ書房、1993年)あたりを読みたい。2021/04/12