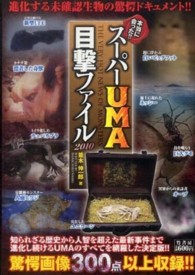内容説明
「まちづくり」「地域おこし」とは、一過性のイベントによって人を集めることではない。日本各地の固有文化を深く掘り起こしつつ、暮らしと産業のなかに活かす人々に注目しよう。創造都市づくりと新しい起業者精神を提起し、ソフト・パワー時代の日本再生を地域から展望する。
目次
1 地域固有の文化資源を見直す都市設計―マルチメディア産業と、創造都市
2 地域文化産業財における「二重の市場」とまちづくり―映像の市場と現地の市場の相互関係
3 「未知」の創造による「まち」の形成―青森、京都からの芸術リポート
4 地域づくりのノウハウの形成と発展―過疎地域における文化・産業政策を中心として
5 産業のまちの文化創造―首都と地域社会から
6 山の文化、自立の文化、そしてクラスターの形成
7 固有の味わいと国際交流―アーツマネージメント・ブームを越えて
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
18
D2の時に読んだ本。阪本先生担当の箇所。地域社会の活性化からみると、職人作業の現場を映像化し、音声を録音して、編集し、広く伝達し、普及して学習した上で、現場を訪問し、かつ、創造的な成果を購入する機会をもつ、という「空間的ひろがり」を視野にいれることが必要(74頁)。経済学なら空間経済学がある。小池先生の箇所。人・もの・情報の流れが悪く動脈硬化に陥りやすい中山間地域に地場のものの流れが、文化育成の下支えとなっている。住民や組織が主体となった永続的なまちづくりは、創造と破壊により、流動化が大切(197頁)。2021/01/28
-

- 電子書籍
- 【単話版】魔王と勇者が時代遅れになりま…
-
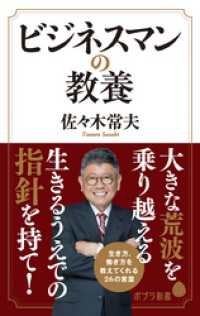
- 電子書籍
- ビジネスマンの教養 ポプラ新書