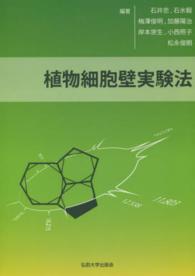出版社内容情報
2022年にはほぼ全ての地銀が赤字に!人口減少、フィンテック時代に淘汰される銀行、生き残る銀行を格付けアナリストが徹底分析
内容説明
7割の地銀ではすでに本業が赤字化、5年後にはほとんどの地銀が赤字経営に転落?!人口減少、フィンテックで「いらなくなった銀行」はどこか?格付けアナリストが大手行の国際比較も交え徹底分析!銀行「大淘汰時代」に生死を分ける「条件」とは?
目次
まえがき 「いま」に重なる戦前の銀行と会社員の姿
第1章 邦銀共通の課題
第2章 地銀問題の本質
第3章 大手行は本当に大丈夫なのか
第4章 なぜ改革が進まないのか
第5章 フィンテックは破壊か救いか?
第6章 「大淘汰時代」をどう生きのびるか
著者等紹介
吉澤亮二[ヨシザワリョウジ]
S&Pグローバル・レーティング金融法人及び公的部門格付部シニア・ディレクター。1987年横浜国立大学経営学部卒業。92年ボストン大学経営大学院(MBA)修了。2001年S&P入社。金融機関格付部の日本のセクターリード・アナリスト。金融機関の全般的な信用力分析に従事。また、全社におけるGlobal Analytical Oversite&Consistency Councilのメンバー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
79
現代新書の「捨てられる銀行」は金融庁がマスコミ記者に書かせたもので全体的な動きは把握できているように思えますが、この本ほど銀行業務には切り込んでいないと感じていました。どうも最近は銀行を巡る本はこのような題名をつけるものが多いので閉口しているのですが、この本の中身はすごくきめ細かく分析をしています。業務の細かなところまで把握していると感じました。最近では読むにたる銀行本の1冊です。2017/12/23
メタボン
29
☆☆☆ 今は良くも悪くも銀行が儲からない時代。大体預金なんかほとんど利息がつかないほど、低金利だし。地銀が信金に退化するというのは極端だけど、地域密着金融として生き残るために一理ある手段かもしれない。3つの地域にグループ化して再編というのは行き過ぎではないか。レジェンド=過去の遺産に見動きが取れない地銀というのは共感。地方の支店の存続はますます困難になる。しかし一番危惧するのは、この書が出版された頃よりも、コロナ禍の今、そしてこの3〜5年後の方が、更に厳しい金融情勢となることだ。2020/08/02
楽
11
17年。格付機関S&Pアナリストの著作だけにデータ分析は細かいが、提言は譬えがピンボケでしっくりこない■銀行の三大業務である預金、貸出、為替はどれも儲からない(と思われている)。スマホ決済が進めば送金のコストはほぼゼロになるし、さらに(ハードルは高いが)給与もポイントで付与されれば個人の預金口座は不要になるかもしれない。いずれにせよ、特に地銀は統合して規模の経済を目指すか(あればの話だが)、地域密着の信金・信組化するしか生き残る道がないのでは。銀行に言えることは他の業種にも言えることで日本全体の「宿痾」か2019/06/15
紫の煙
8
かつて地方の優良就職先だった地方銀行が、岐路に立っている。フィンテックにより地域性が意味をなさなくなる、構造的な低収益の問題。地方銀行グループは3つでよい。または、相互扶助組織である信組への組織変更を提唱。2018/02/10
kenitirokikuti
8
表題に反し、真面目な良著と聞き購入。著者はS&Pグローバル・レーティングのシニアディレクター▲フィンテックは〈金融業界の関係者が「職業に対する忠誠心(会社に対する忠誠心ではない)を正しく保持できれば…日本の金融業界を力強く甦らせる良い契機になるはずである〉p7▲〈企業統治の基本精神は、健全な相互牽制機能を働かせることにある。…相互に従属的でない独立した個人や部署が確立して、はじめて十分に機能するのではないか。〉p.112▲「目安箱」がないため〈怪文書という…内部告発文書が社内外に出回る〉p.1192017/12/31