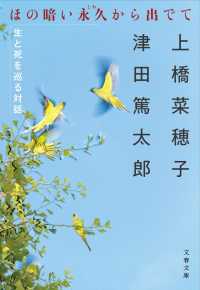出版社内容情報
社会歴史学者・小熊英二の時評集、待望の第2弾。原発、レイシズム、日本国憲法、民主主義。日本のこれからを考察。
内容説明
東日本大震災により社会変化が顕在化した。「私たちのこれから」をめぐり、各地で次の時代に向けた新たな試みがいくつもはじまっている。デモが全国でおこり、国会周辺で人々が声を上げる姿は日常となった。過疎化と人口減、経済閉塞、ポピュリズム、東京五輪、改憲、マンガ産業などを包括的な時代把握、冷徹な視線で読みとく時評集。
目次
1(凡庸でナンセンスな領土問題;東京五輪 いくつかの概念;外国語不要 国内依存の日米経済 ほか)
2(島根の軽トラ市 地域の悩みチャンスに;廃校利用宿舎 地元愛で持続;水俣「環境モデル都市」へ転換模索 ほか)
3(憲法九条;保守とリベラル;「六八年」と「八九年」 ほか)
著者等紹介
小熊英二[オグマエイジ]
1962年、東京生まれ。1987年、東京大学農学部卒業。出版社勤務を経て1998年、東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻博士課程修了。現在、慶應義塾大学総合政策学部教員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
勝浩1958
14
新聞は時間的制約があって自分の関心の強い分野しかじっくり読まないので、このように論点がまとめられているのはありがたい。いま日本の社会でどのようなことが起こっていて、なにが大きな問題になり、政府や各種行政機関やあるいは市民団体や地域のコミュニティはどのように対応しているのかが分かってくる。大事なことは「お上」に丸投げしないことなのです。わたしたちひとりひとりが、もっと政治や社会にコミットしていかなくてはならないのですが、分かっていてもなかなか十分にはいかないのが現状でしょうか。2016/09/10
yoneyama
12
2011年から2015年にかけて、社会構造の変化に注目して書いた小熊氏の時評を集めたもの。この時期、朝日新聞の論壇委員を勤めて、経済誌や保守系雑誌も含めた雑誌をよく読んだとのこと。この時期の社会構造の変化、社会運動の変化はやはり震災と原発事故、安保法制を機会に、日本の安定性、持続性に関する危機感が人々を駆り立てたのではないかとのこと。学者として、この時期の社会運動の推移を注視しコメントしていた著者の評は今読んでまた価値がある。2024/09/28
4
「恐らく、くだんの牛丼チェーン店の経営者は、日本の労働者のモラルを、不変の前提と考えていたのだろう。言葉を換えれば、甘えていたともいえる。安くこき使っても高いモラルで働いてくれるはずだ、と何の根拠もなく思い込んでいたなら、それは甘え以外の何物でもない。労働者のモラルに甘えてコストカットしたあげくに、店舗閉鎖という形で、かえって高いコストを払うことになった。『最近の若者は甘えている』と発言する経営者が時々いるが、甘えているのはどちらの側か、よく考えてみた方がよい」2019/02/23
紅葉まんじゅう
2
「私が戦争が嫌いなのは社会の雰囲気が悪くなるからです。戦争になると、必ず分断と格差がおきる。死ぬ人と死なない人、戦場に行く人と行かない人、戦争で利益を得る人と損害を受ける人。社会の中で何重にも分断が生じ、雰囲気が悪くなる。アメリカでベトナム戦争が疎まれたのも、大学生でないもの、さらに大学生でも成績が悪いものから徴兵され、分断と怨嗟を生んだことが一因でした。」 私は戦争には反対だが、明確な理由を言語化するのは案外難しい(人を殺すべきではない、に留まってしまう)。この本は結構参考になった。2022/03/27
とくけんちょ
2
相変わらず論理が明快!テーマは出版、政治、法律まで幅広いが、筆者の主張はわかりやすい。最後のテーマでも述べられているが、筆者は編集者としての経験から自分がわからないものは人にわからないという目線で編集していたと。これは自分の主張にあっても、客観視するということに繋がっているようである。どのテーマをとっても、つまるところ何なの?に比較的、答えを出してくれている。2017/11/22
-

- 電子書籍
- 御社にそのシステムは不要です。 中小企…
-
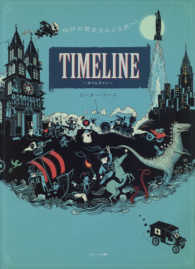
- 和書
- TIMELINE