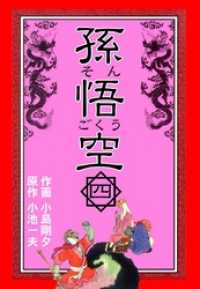出版社内容情報
近年、中高生の英語力を伸ばしている東京都。その背景には一体何があるのか。
「話すこと」の評価が行われずに来たのは、適切な方法が見つからずそれができなかったからにすぎない。現在は、ICTや既存の蓄積されたノウハウの活用などの工夫により、それが可能となっている。英語は実技の側面が強い。暗記や読解は苦手でも、聞いたり話したりするコミュニケーションは得意な生徒もいる。そのような生徒を適切に評価しないのは不作為による過誤とさえ言えるのではないか。
スピーキング・テスト――いまやらなければ、日本の英語教育はさらに10年遅れてしまう。
内容説明
ガラパゴス入試からの脱却。近年、中高生の英語力を伸ばしている東京都。その背景には一体何があるのか。
目次
第一部 英語力と学校・入試(日本人にとっての英語;生徒の英語力と、学校での英語教育の現在地)
第二部 東京都のスピーキング・テストとは(スピーキング・テスト導入までの道のり;東京都のスピーキング・テスト(ESAT‐J)とは
スピーキング・テスト(ESAT‐J)の基本的成り立ちや特徴)
第三部 スピーキング・テストのインパクト(スピーキング・テスト(ESAT‐J)導入後の経過
スピーキング・テスト(ESAT‐J)実施のインパクト:中学校
スピーキング・テスト(ESAT‐J)実施のインパクト:地区教育委員会)
第四部 入試改革を取り巻く様相(2020大学入試改革との符合;論争の真相)
付録 スピーキングの力を伸ばすためのTIPS
著者等紹介
瀧沢佳宏[タキザワヨシヒロ]
東京都教育庁教育監、東京都教職員研修センター所長。都立高等学校の英語科教員、管理職、米国カリフォルニア州派遣等を経て、東京都教育庁に勤務。高校教育や教員採用、オリンピック・パラリンピック教育等のほか、おもに英語教育・国際教育や高校改革を担当。都独自の留学制度の創設やTokyo Global Gatewayの設立、ESAT‐Jの導入、国際バカロレア校の設置などに携わる。令和6(2024)年4月から現職。北陸大学経済経営学部講師、京都橘大学通信教育心理学科講師、早稲田大学総合研究機構総合政策科学研究所招聘研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Riopapa
taverna77