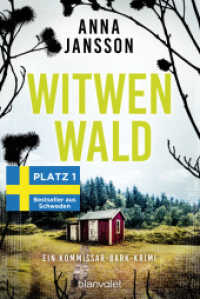出版社内容情報
日本人の多くが自らを「無宗教」だと考えているにもかかわらず、「墓参り」や「初詣」を始めとする宗教行動が盛んなのはなぜか?
人気宗教学者が日本人の「信仰のあり方」を、歴史的な側面を踏まえながら多角的に考察する。
日本人の宗教観がよくわかる本。
第一章 無宗教化する世界
経済発展で「宗教」が変わる
無宗教化する世界のなかで…
第二章 日本人は本当に無宗教なのか
男性は50代で信仰に目覚める
メッカ巡礼より多い日本の初詣
墓参りも初詣も新しい習慣
実は宗教的な日本人…
第三章 なぜ日本人は無宗教だと思うのか
キリスト教の布教に立ちはだかった仏教という壁
神仏分離が生んだ無宗教
新宗教の強引な布教が宗教のイメージを悪化させた…
第四章 道徳の源泉としての武士道と天皇
新渡戸の「武士道」と無宗教
伊藤は皇室に日本国憲法の機軸を求めた…
第五章 日本宗教の厚みと深み
GHQは「国家神道」の意味を誤解した
神社は日本独特の神聖なる空間…
第六章 いったい日本人は何を信じてきたのか
日本人にとっての「無」
「戒律」の厳しい日本という国…
内容説明
仏教も神道も熱心に受け入れながら、なぜか「無宗教」と感じてしまう。いったい日本人は何を信じてきたのか?宗教を理解するためにも、信仰のあり方を見つめ直す。日本人の宗教観を解き明かす。
目次
第1章 無宗教化する世界
第2章 日本人は本当に無宗教なのか
第3章 なぜ日本人は無宗教だと思うのか
第4章 道徳の源泉としての武士道と天皇
第5章 日本宗教の厚みと深み
第6章 いったい日本人は何を信じてきたのか
著者等紹介
島田裕巳[シマダヒロミ]
1953年東京生まれ。作家、宗教学者。東京大学文学部宗教学科卒業。同大学大学院人文科学研究科修士課程修了後、博士課程修了(宗教学専攻)。東京女子大学教授。東京大学先端科学技術研究センター客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
紅咲文庫
makio37
kenitirokikuti
はな