内容説明
味噌汁26%、天ぷらそば22%…。和食さえも国産食材で作れないニッポン。間近に迫り来る世界的食料不足!自給率40%の「待ったなし!」状況に私たちは何をすべきか?この国の食料安全保障のキーマンが語る。
目次
序章 食料自給率を通じて見えてくるもの
第1章 食料自給率四〇%の実状
第2章 食料自給率の低下がわが国に与える影響
第3章 食料自給率の低下が世界に与える影響
第4章 世界の食料事情と厳しくなるわが国の食料調達
第5章 これからのわが国の食料安全保障
第6章 食料自給率向上のために、今、できること
著者等紹介
末松広行[スエマツヒロユキ]
農林水産省大臣官房食料安全保障課長。東京農業大学客員教授。埼玉県出身。1983年東京大学法学部卒。農林水産省入省後、国土防災、地方行政(長崎県諌早市)、漁業交渉、金融問題、米問題、食品リサイクルなどを担当する。中川昭一農林水産大臣秘書官事務取扱、小泉官邸内閣参事官、農林水産省環境政策課長、同企画評価課長などを歴任。バイオマス・ニッポンを提唱(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
masabi
12
食料自給率には複数の算出方法があり、日本が採用しているのは、カロリーベースのものだ。自給率の算定には国産の畜産であっても外国から飼料を輸入する場合には自給率にカウントしないなど、今まで知らないことが書かれており良かった。自給率の低下がもたらす問題は、冒頭で書かれた通り食料という生命を支える物を他国に委ねてしまうことだろう。世界人口の増大、食料の需要増は世界で食料の奪い合いを起こし、輸出規制によってお金があっても食料調達に困窮することもあり得る。2016/01/31
スダタロー
5
10年前の著書となりますが、著者は現在、事務次官になられました。 レビューを見ると、語り口に曖昧さがあるという指摘もありますが、食料自給率を切り口とした日本農業についての、著者の描くグランドデザインの話と受け取りました。農業を語る上で求められる国家観というものを感じます。 ちなみに、2017年の食料自給率は38%。増えるどころか減っています。畜産物への飼料用米の供与は一部では行われているものの、必ずしも取り組みは順調というわけではありませんね。2018/08/25
タケノコにょっき
3
2008年の本だけど、いまだに続く課題であるので参考になった。コロナ禍により世界物流が歪んでいる中、食料自給率について考えさせられる。実際、ポテトですら供給制限中。万が一日本への食料供給が寸断されてしまった場合の1日の食事イメージが参考になった。(めちゃめちゃお芋を食べないと必要カロリーが取れないらしい) 日々の消費の選択は応援・支援であるし、考えて選びたい。日本の食料自給率向上が難しい理由として、日本人の食の嗜好が安定しないからというのが興味深かった。たしかに。家庭内でも同じものを食べてないな。2022/02/05
サカモトマコト(きょろちゃん)
2
食料自給率の入門書。 出版されてからかなり時間がたっているため本の中で紹介されてるデータなどは古いのですが。食料自給率の算出方法や日本の食料自給率が下がってしまった原因など今でも役に立つであろう情報が載っていました。2017/02/04
ねっしー
2
食料自給率について、分かりやすく書かれた一冊。著者が農水省勤務なので、日本の農業政策についても詳しく記載されている。ただし、著者自身の意見は抽象的でほぼ書いていない。基本用語を知りたい人にはオススメ、批判的な見方や具体策が読みたい人は別の本をすすめる。2016/09/12
-

- 和書
- 誘惑者 〈下〉
-

- 電子書籍
- 政略婚皇后は復讐の毒に咲く 21話「お…
-
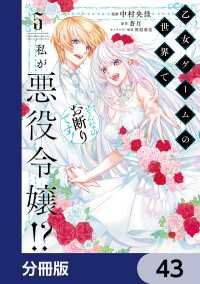
- 電子書籍
- 乙女ゲームの世界で私が悪役令嬢!? そ…
-
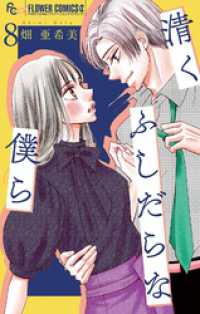
- 電子書籍
- 清くふしだらな僕ら【マイクロ】(8) …
-
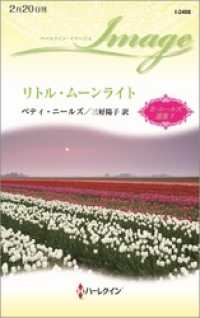
- 電子書籍
- リトル・ムーンライト ベティ・ニールズ…




