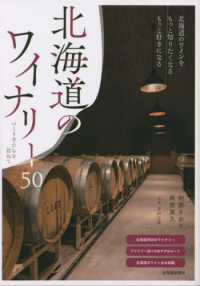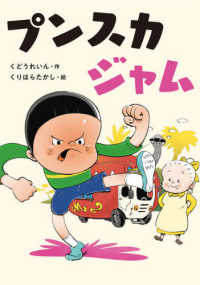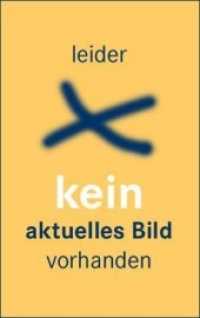出版社内容情報
様々な人がくらしやすい町にするために、必要なものとは? 社会のバリアをなくすために必要な「心のバリアフリー」のヒントが満載。 いま元気な人も、いずれ歳を取ります。また、とつぜんの病気や事故などで、「あたりまえ」の生活が送れなくなる可能性もあります。そう考えると「バリアフリー」は、障害者や高齢者だけでなく、すべての人に関わる問題です。これまでも、バリアフリーやユニバーサルデザインの考え方で、さまざまな施設や商品、サービスなどが作られてきました。しかし、まだ日常生活にバリアを感じている人がいます。
「心のバリア」とは、〈思いこみ〉や〈偏見〉だけではありません。「だれもがくらしやすい社会」を実現するために、あなたが、社会によって生み出されたバリアや、自分の心のバリアに気づき、考え、行動することを「心のバリアフリー」と言います。本書では、当事者の声を聞き、困っている人を見かけたときに、だれもが行動を起こせるようなヒントや実践例を多数掲載しました。道徳やインクルーシブ教育などでも、必ず役に立つ1冊。
中野泰志[ナカノヤスシ]
監修
内容説明
障害のある人のことを理解し、やさしく接すれば、「バリア」はなくなると思いますか?残念ながら、それだけでは「バリア」はなくなりません。なぜなら、障害のある人のまわりに、いつもやさしい人がいるとは限りません。また、やさしい人がいなければ自由に活動できない状況は、自由とは言えませんよね。では、だれもが自由に活動できる社会をつくるには、どうすればよいのでしょう?本書では、さまざまなバリアを感じている当事者の声を聞き、こまっている人を見かけたときに行動を起こせるように、ヒントや実践例を多数紹介しています。
目次
第1章 みんながくらす町(ちょっとの段差で、たいへん!;点字ブロックや白杖は、何のため? ほか)
第2章 乗り物で出かけよう(きっぷを買って、改札へ;ホームまでは、何で行く? ほか)
第3章 学校を見てみよう(どんな子がいるかな?;目が見えにくい友だちのことを知ろう! ほか)
第4章 いろいろな場所へ行こう(スタジアムへ行こう!;映画やコンサートを楽しもう! ほか)
第5章 パラリンピックを楽しもう!(パラリンピックはこんな大会!;競技を知ろう!体験しよう ほか)
著者等紹介
中野泰志[ナカノヤスシ]
慶應義塾大学経済学部教授。国立特殊教育総合研究所(現・国立特別支援教育総研究所)視覚障害教育研究部研究員、慶應義塾大学経済学部助教授、東京大学先端科学技術研究センターバリアフリープロジェクト特任教授を経て、2006年より現職。専門は「知覚心理学」「障害者(児)心理学」「特別支援教育」。『ユニバーサルデザイン2020関係府省等連絡会議「心のバリアフリー分科会」』のメンバーであり、内閣官房の『「心のバリアフリー」を学ぶアニメーションの教材』や『「心のバリアフリー」に向けた汎用性のある研修プログラム』の座長を担当した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆうぴょん
Oliver
mame
-

- 和書
- ケベックの歴史