出版社内容情報
鳴海 風[ナルミフウ]
著・文・その他
おとない ちあき[オトナイチアキ]
イラスト
内容説明
1871年(明治4)11月12日、横浜港からアメリカに向けて出港した100人を超える使節団。使節団には、日本初の5人の女子留学生が同行しました。永井繁子、津田梅子、山川捨松、上田悌子、そして、吉益亮子。のちの日本の女性教育、社会進出に大きな役割を果たした彼女たちは、いったいどんな少女だったのでしょう?本書は、吉益亮子を主人公のモデルに、外国で学ぶ夢を実現させたひとりの少女の姿を描く物語です。
著者等紹介
鳴海風[ナルミフウ]
1953年新潟県生まれ。自動車部品メーカーのデンソーで生産技術を研究するかたわら、江戸時代の数学「和算」を題材にした小説などを多く発表。『円周率を計算した男』(新人物往来社)は、第16回歴史文学賞、2006年日本数学会出版賞。『円周率の謎を追う 江戸の天才数学者・関孝和の挑戦』(くもん出版)は、第63回青少年読書感想文全国コンクール中学校の部課題図書
おとないちあき[オトナイチアキ]
1988年生まれ。一般文芸書や児童書など幅広いジャンルで、装画・挿絵を手がけている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
chiaki
31
明治4年、日本で最初の女子留学生として岩倉使節団に同行し、アメリカに留学した吉益亮子(そら)を主人公にしたフィクション。攘夷思想の渦巻く幕末において、津山藩医師で洋学者の箕作阮甫の孫大六との出会いから語学に興味を抱く。タイトルにもつながる「世界は広くて遠いけど、青空は繋がっている」ことを意識したそらの心情など、もっと丁寧に描かれていればなぁ。留学の動機や渡米の苦労、渡米後の活躍についてはほとんど触れられておらず、物語後半部分に物足りなさを感じた。少し触れられていた北方領土問題、その歴史の深さに驚きました。2022/04/11
くぅたん
9
爽やか。江戸末期、海外留学に憧れる少女の物語。日本初の女子留学生5人のうちの一人、吉益亮子をモデルにしたフィクション。「怪異研究事始め」「はなのまちオペラ」と一緒に展示して、江戸、明治、大正の時代を味わってもらいたい。2022/10/18
雪丸 風人
7
日本最初の女子留学生の一人をモデルにした伝記風の創作です。勝ち気で好奇心旺盛な町医者の娘が、異国事情に通じる武士の子弟と知り合い、関わるうちに、みずからも学びに目覚めていきます。女性の地位が低く、子どもでも当然のように働いていた時代が描かれているので、今の子の目には新鮮に映るかもしれませんね。私には、たがいを気づかい、助け合う長屋の人々の生き様が印象的でした。主人公の少女はとびきり活き活きと描かれていますが、ラストで実在の人物に繋げない方がスッキリ楽しめたような気もします。(対象年齢は12歳以上かな?)2022/06/28
読書国の仮住まい
6
明治四年、アメリカに派遣された使節団に五人の女子留学生がいた。 後に津田塾を創立する津田梅子、大山巌の妻となり鹿鳴館の華と称される山川捨松、それぞれ学校の教師となる永井繁子と上田悌子。 その中にあって女子英学教習所を作ったくらいしか業績の分からない吉益亮子。 著者によるとここからが小説家の仕事。 海外留学を決意できたのはその経験者がいたのだろう。 津山藩医師箕作阮甫の孫大六と知り合う機会もあったろう。 肝心の留学は病気のため、十ヶ月ほどで帰国らしい。 世界は広くて遠いと思っていたけど、その気になれば近い。2022/09/09
いよの缶詰め
6
明治4年、五人の少女がアメリカへ旅立った。永井繁子や上田悌子、山川捨松。そしてお札の人になる津田梅子。しかし主人公は吉益亮子だ。帰国後、彼女も女子の英語の学校を作るも、当時流行したコレラで亡くなってしまい、その後不明。梅子達に目が行きがちになっているのは事実だが、彼女(亮子)もいたんだぞと言われているような気がした。彼女についての情報は少ないが、様々な情報を寄せ集めて彼女(そら)が誕生した。自分を変えるきっかけは近くに落ちていた。読んでいる途中、幕末や明治初期を舞台にした大河ドラマが出てくる2022/06/11
-

- 電子書籍
- 継母に可愛くないと育てられた私が公爵子…
-

- 電子書籍
- サイレント・ウィッチ【ノベル分冊版】 …
-
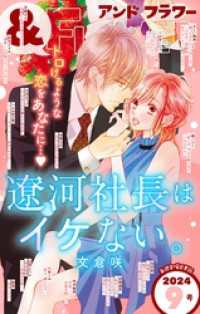
- 電子書籍
- &フラワー 2024年9号 &フラワー
-

- 電子書籍
- 魔眼の復讐者 ブラッドパラサイト【タテ…
-
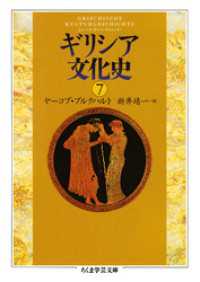
- 電子書籍
- ギリシア文化史7 ちくま学芸文庫




