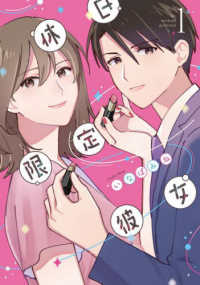出版社内容情報
AI、友だち、サイコパス、同性愛――身近な思考実験を通して、常識を疑うための4ステップが身につく哲学思考入門!
内容説明
AI、友だち、サイコパス、同性愛―。身近な思考実験を通して、常識を疑うための4ステップが身につく!
目次
第1部 生きるとは、考えること―哲学者以前の君へ(生きること、考えること;「わかった」風の大人たちを疑え;ソクラテスはなぜ死刑になったのか?;子どもは生まれながらに「哲学者」なのか?;常識を知ったときにはじめて「哲学」がはじまる ほか)
第2部 考え抜くためのレッスン―直感からはじめる8つの思考実験(「コピペ」を考える―パクリはいけないことなのか?;「個性」を考える―ほんとうの自分は存在するか?;「サイコパス」を考える―共感できるのはいいことか?;「同性愛」を考える―なぜ認められないのか?;「友だち」を考える―どこからが敵なのか? ほか)
著者等紹介
岡本裕一朗[オカモトユウイチロウ]
1954年福岡県生まれ。玉川大学文学部名誉教授。九州大学大学院文学研究科哲学・倫理学専攻修了。博士(文学)。九州大学助手、玉川大学文学部教授を経て、2019年より現職。西洋の近現代哲学を専門とするが興味関心は幅広く、哲学とテクノロジーの領域横断的な研究をしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
57
数年前から、自分の中のキーワードの一つが哲学。情報が溢れ、簡単に手に入る今という時代だからこそ、哲学の必要性が大きくなっている。基本は、自分の頭で考え抜くことだと思う。表面的なハウツーとか、今だけのもので済ませてしまう傾向が強いと感じている。人は退化し始めているのではないか。答えを安易に求めてしまう、我慢ができないからだろう。自分の頭で考え、時間をおいて、また考える。この繰り返し。2021/09/18
タナカ電子出版
37
使えない哲学から使える哲学へ☺️真理よりも妥当性が人々に受け入れられる✨ソクラテスはなぜ死刑になったのか?禁酒法はなぜ撤廃されたのか?これらの共通性は人間は真理や哲学的合理性よりも打算的で妥当な感情論に流される生き物だから…よって本書は哲学的に考えながら最終的は真理よりも打算的で妥当な方向性を取る👀‼️哲学反逆本の印象が否めないけど、実践的哲学📖なのです🎵①直感をもとに立場を決める。②根拠に説得力を持たせる。③別の観点から問い直す。④使える結論を導きだす。2020/04/10
テツ
21
大学を卒業してからも定期的に哲学塾に通うような拗らせる日々の中で身についた役に立つ何かを挙げるとしたら、世の中の大抵の問題には答えなど出せないと気づいたということ。人は易々と真理になど到達できないということ。哲学をやることで白黒つけなければ不安で仕方がないというメンタリティは矯正されるだろうな。簡単に立ち位置を定めてしまうような逃避的な精神活動からは思考する力が削ぎ落とされていく。辛くても苦しくても考え続けるんだ。例えその責苦が永遠に続くとしても。2021/09/19
ta_chanko
15
生きるとは、考えること。コピペ・個性・サイコパス・同性愛・友だち・AI・転売・仕事について、その本質や性質について深く掘り下げて吟味し、その是非について考える。なぜ、○○なのか?社会常識・法規範に囚われて思考停止に陥るのではなく、倫理や本質について考え抜く。AI時代を迎えるにあたって、哲学的に考えることは必須の能力。さもなくば「無用者階級」に。work(仕事)> labor(労働)。2020/02/14
ジコボー
15
はじめての哲学の本と言った内容。知っている事を知らないフリをする「アイロニー」。これが哲学のスタートとも言えますが、日常の生活では、これはとても嫌味なモノ。哲学とは他人に嫌われる事だと言っていますが、まさにその通りだと思います。 「前提を考え直す」「ディベート的な思考法」は日本では敬遠されがちですが、それこそ今の日本に足りないものだと思います。 子供は哲学者だと言われていますが、知ってて敢えて聞くと知らないから聞くでは全く違います。型があればこその型破り、かたなしにならない様自分も学び続けようと思います。2019/12/22
-

- 和書
- アメリカの歴史 2