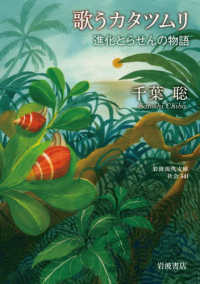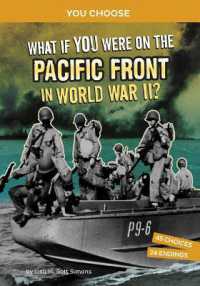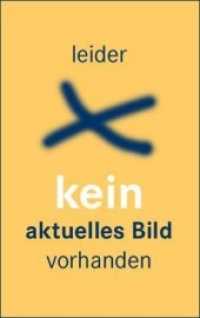内容説明
謀叛に失敗し島に流された男が、絶望のなかに新たな人生の境地を見出していく菊池寛の『俊寛』。巨大な体躯に釣り合わぬ童顔、工場に新たに雇われた男はうまくしゃべることもできなかったが…。忍耐と誠実でついに絶大な信頼を勝ちとっていく男の物語(八木義徳『劉廣福』)。異国で燈台守となった老人は四百段以上もあるらせん階段を上り下りする孤独な仕事に精励するが…。一瞬の油断がまねいた悲劇(シェンキェヴィチ『燈台守』)。運命の波に襲われた人間たちの生き方。
著者等紹介
菊池寛[キクチカン]
1888‐1948。香川県生まれ。一高、京大時代から作品を発表。新聞小説『真珠夫人』が爆発的にヒットし、後に「文藝春秋」や「オール讀物」を創刊。芥川賞、直木賞を創設するなど、文壇ジャーナリズムの始祖となった
八木義徳[ヤギヨシノリ]
1911‐1999。北海道・室蘭生まれ。早稲田大学在学中から横光利一に師事。満州での生活を題材にした『劉廣福』で、1944年に芥川賞を受賞。創作への真摯さで「最後の文士」とも呼ばれた
シェンキェヴィチ[シェンキェヴィチ][Sienkiewicz,Henryk]
1846‐1916。ポーランドの小説家。大学時代から週刊誌や新聞で小説を発表し始め、1895年、皇帝ネロ統治下のローマを描いた『クオ・ヴァディス』で世界的に名を馳せる。1905年にノーベル文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
新地学@児童書病発動中
アルピニア
モモ
神太郎
-
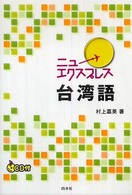
- 和書
- ニューエクスプレス台湾語