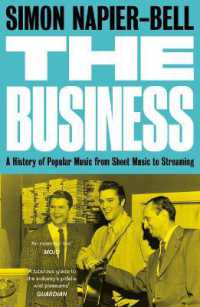出版社内容情報
地味でパッとしないカタツムリだが、生物進化の研究においては欠くべからざる華だった。偶然と必然、連続と不連続……。木村資生やグールドらによる論争の歴史をたどりつつ、行きつ戻りつする研究の営みとカタツムリの進化を重ねて描き、らせん状の壮大な歴史絵巻を織り上げる。第71回毎日出版文化賞受賞作。解説=河田雅圭
内容説明
なんだか地味でパッとしないカタツムリだが、生物進化の研究においては欠くべからざる華だった。偶然と必然、連続と不連続…。木村資生やグールドらによる論争の歴史をたどりつつ、行きつ戻りつする研究の営みとカタツムリの進化を重ねて描き、らせん状の壮大な歴史絵巻を織り上げる。第71回毎日出版文化賞受賞作。
目次
1 歌うカタツムリ
2 選択と偶然
3 大蝸牛論争
4 日暮れて道遠し
5 自然はしばしば複雑である
6 進化の小宇宙
7 貝と麻雀
8 東洋のガラパゴス
9 一枚のコイン
著者等紹介
千葉聡[チバサトシ]
東北大学東北アジア研究センター教授、東北大学大学院生命科学研究科教授(兼任)。1960年生まれ。東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。静岡大学助手、東北大学准教授などを経て現職。専門は進化生物学と生態学。大学院修士課程でカタマイマイに出会い、小笠原諸島を出発点に、北はシベリア、南はニュージーランドまで、世界中のカタツムリを相手に研究を進める。本作で2017年度の毎日出版文化賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マエダ
ふるい
in medio tutissimus ibis.
zhiyang
家の中のぱっぽ