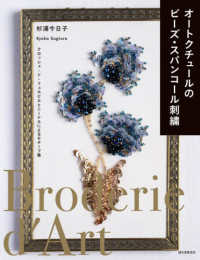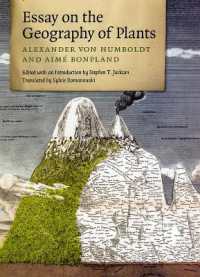目次
第1章 刀剣の歴史
第2章 アーサー王のエクスキャリバー
第3章 ベーオウルフ
第4章 剣巻
第5章 白鳥になった英雄―ヤマトタケル
第6章 羅生門の鬼とグレンデル
終章 結論に代えて―剣の思想の背後にあるもの
著者等紹介
多ヶ谷有子[タガヤユウコ]
栃木県出身。東京都立大学大学院博士課程単位取得満期退学。現在、関東学院大学文学部英米文学科教授。英文学を中心とした中世ヨーロッパ文学、日欧の対照を中心とした比較文学、比較文化学を研究。現在、『記紀』、『平家物語』などの日本の古典と、アーサー王伝説、宗教文学、バラッド、ロマンスなど英国を中心とするヨーロッパの中世文学を資料に、暦と文学、鬼と妖怪の文化史、煉獄と地獄などのテーマで研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
in medio tutissimus ibis.
2
物語の剣には理想が仮託されている。本書はアーサー王の個人の英雄の資質の象徴としてのエクスキャリバー、ベーオウルフ英雄譚における王権の無能の象徴としての剣、平家物語剣巻における源氏棟梁の王爾としての名剣と、天皇家の神器たる草薙剣の伝承を担うヤマトタケルをそれぞれ見たのち、息子の腕を取り返しに来たグレンデルの母と羅城門の鬼伝説とに共通する剣の取返し/借りた剣のモチーフなどを探っていく。小碓命の碓は一本動かしたら白+隹なので最後に白鳥に化身することが寓意されていて、物語の所々で鳥のモチーフの登場人物あらわれる。2024/11/17
Oltmk
2
歴史上における剣の成立やヤマトタケル伝承とベーオウルフの比較、アーサー王伝説の剣を返した意味やあまり注目される事の無かった剣巻が初めて知る情報で興味深かったがヤマトタケル伝承の成立過程での論の組み立てで強引さを感じてしまった。 個人的に全体としての完成度は高いと思うのだが、渡辺綱伝説とベーオウルフ研究の所で伝承過程を描くためもう少し伝承比較をしてほしかったというのはある。 2019/12/08
あを
2
先日読んだ本のついでに題名が面白そうだったので借りてしまった。自分は学生時代にこういう分野とは全く畑違いのことを勉強しており、それと比較すると、論理の組み立て方や解の得かたが全く違う所が面白い。2015/01/09
YUSENA
0
自分がやりたいと思っていた研究分野で同じ方向性の書だったので手に取る、剣をキーワードに文献の叙述から人々の思想を読み解いていく。 あとがきで触れられていたがヤマトタケルの内容に偏ってしまったことが残念、3つの物語からの総括内容を強く記して欲しかった。2013/12/12
-
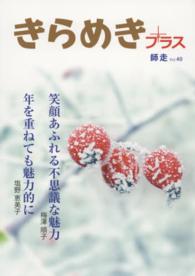
- 和書
- きらめきプラス 40