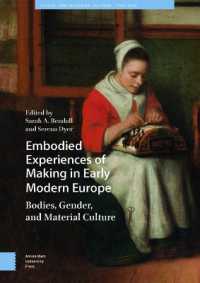内容説明
近世から近代にかけての水陸交通運輸の発達と変遷を体系的にとらえようとした著者の多年にわたる研究成果、鉄道が発達する前夜、人や物は川船や船頭、馬方によって河川や道路をどのように運ばれていたのか。第一編の「水上交通」では利根川水系の河岸問屋・廻船問屋が扱った城米や紅花、鰯等の多彩な商品について、水揚帳や送り状などをもとに運送料や輸送範囲まで詳細に検討する。第二編の「陸上交通」ではさまざまな街道の宿駅や問屋、助郷における人馬調達の負担ぶりと、免除を求める嘆願書を示し、困窮に追い込まれる農民の姿を浮かび上がらせる。
目次
第1編 水上交通(利根川水運の展開;近世河川海上運漕と江戸廻船問屋―利根川・荒川の舟運荷物を中心として;水戸天狗党の乱と利根川舟運―幕府鎮圧軍の軍需物資運漕;明治前期の内陸水運と道路輸送―上利根川水系の河岸場を中心として;明治前期の下利根川水運と商品流通―総州高田河岸宮城家文書を中心として)
第2編 陸上交通(近世宿駅問屋制の確立過程再論―問屋の宿役人化をめぐって;日光御成道大門宿の研究―特権大通行と人馬継立・休泊の負担;水戸道中における特権大通行とその負担―取手・藤代両宿を中心として;近世後期木下街道の在郷商人―商品物資の生産・販売と輸送;幕末維新期の助郷負担―武州多摩郡の村々を中心として)
著者等紹介
丹治健蔵[タンジケンゾウ]
1927年、東京都に生まれる。1952年法政大学文学部史学科卒業、その後大学院博士課程修了。法政大学文学部研究助手・同大学兼任講師、青山学院大学文学部・埼玉大学教育学部の兼任講師、与野市史編さん委員長、日の出町史専門委員長、交通史研究会監事等を歴任し、現在交通史研究会顧問、文学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。