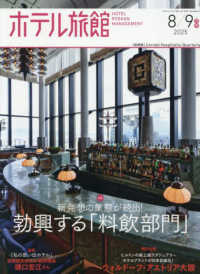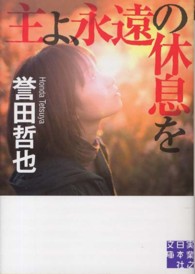- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
出版社内容情報
江戸時代の初めに発明された、食物繊維の王様「寒天」。誰もが知る食品としてのみならず、医療現場や各種製造業でも素材として幅広く用いられている一方で、その歴史はほとんど知られていない。古代より伝わる心太(トコロテン)の歴史を皮切りに、摂津、薩摩、信州、天城、岐阜における寒天産業の盛衰をつぶさにたどり、樺太での寒天をめぐる知られざる闘争までを描き出す、本邦初の本格通史。
内容説明
古代より伝わる心太(トコロテン)の歴史を皮切りに、摂津、薩摩、信州、天城、岐阜における寒天産業の盛衰をつぶさにたどり、樺太での寒天をめぐる知られざる闘争までを描き出す。製造工程がひと目でわかる、カラー口絵8頁付。
目次
第1章 トコロテンの歴史
第2章 寒天の発明
第3章 摂津の寒天
第4章 薩摩の寒天
第5章 信州の寒天
第6章 天城の寒天
第7章 岐阜の寒天
第8章 樺太の寒天(前編)
第9章 樺太の寒天(後編)
第10章 サハリンに日本人寒天遺跡を訪ねて
著者等紹介
中村弘行[ナカムラヒロユキ]
1952年、三重県に生まれる。県立伊勢高校卒業後、東京教育大学、筑波大学大学院で教育学を学び、小田原短期大学食物栄養学科で39年間教員生活を送る。2015年から寒天研究を始め、調査のため、南は宮崎県から北はサハリンまで歩きまわった(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鯖
13
遣唐使により用法がもたらされた心太と、心太から江戸時代につくられた寒天。寒天の生産量日本一は寒晒しの技法を活かす長野。他に伊豆や北海道、植民地化の朝鮮、サハリン等での寒天製作の歴史が記される。明治初期に寒天を製造し地場産業として定着しかけたら、銀行条例によって寒天を作ってた銀行類似会社が銀行に格上げされたことにより、大蔵省から銀行が生産や起業するのは銀行の本務外だから廃止しろってお達しが出て7年で寒天産業が廃止されちゃった伊豆の天城もったいなさすぎる…。会社分割みたいな制度で抜け道無理だったんかな…。2025/04/02
takao
4
トコロテンのルーツはインドネシアなどの南方諸島にあり、中国に伝わり、日本には遣唐使によって製法がもたらされた。寒天はトコロテンを凍結、融解、乾燥させたもので江戸時代の初期に京都で発明された。 2023/10/23
Hiroki Nishizumi
1
学術的な本であるが、思いの外既知の内容が多かった。ところてんの読み方は結局よくわからない変遷だ。2024/04/16