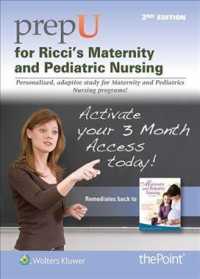内容説明
天然分布の状況から各地の栽培・育種、利用にいたる歩みを、弥生時代から今日までの人間の営みの中でとらえなおす。秋田杉・北山杉・吉野杉をはじめとする産地形成の経緯、藩による林業の育成と禁制、戦争や災害による荒廃におよぶ。
目次
序章 杉の文化史への誘い
第1章 杉の生態
第2章 日本文化形成期の杉
第3章 近世の領主と杉
第4章 杉植林の進展とその背景
著者等紹介
有岡利幸[アリオカトシユキ]
1937年、岡山県に生まれる。1956年から1993年まで大阪営林局で国有林における森林の育成・経営計画業務などに従事。1993~2003年3月まで近畿大学総務部総務課に勤務。2003年より(財)水利科学研究所客員研究員。1993年第38回林業技術賞受賞。著書に『松と日本人』(人文書院、1993、第47回毎日出版文化賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
22
(p.250)戦時中は「国が敗れて森林の存在に何の意義があるのか」とさえ言われ、木材・薪炭生産を至上命令としていた。◉(p.254)昭和26年には新しい「森林法」が公布され…(このころ)拡大造林の担い手は、薪炭林の伐採跡地などを対象とした中小規模の森林所有者の家族労働によるものが主体であった。◉(p.257)昭和30年代にはいってから…薪炭生産の大幅な減少…牛馬の飼料/草山の必要性が失われ…「部落」「財産区」有林の採草地への植林が争うようにはじまり…山間部の田畑は次々と山と化していった。2021/05/20
まづだ
0
「杉」というど真ん中なタイトルから、樹木材木としての杉全般について書かれているのかな、と思ったら期待外れ。杉の歴史、それも生産と流通に焦点をあてています。主に文献による調査が主なので、実学とは遠く教養のための一冊。しかし、それゆえに普段触れない知識がつまっていて面白い!特に江戸時代の伐採規制と罰則、藩の財政事情なんかは、林業藩の間で比べると力の置きどころがかなり違っていて、個性豊か。気づいたら読み進めてしまっている一冊でした。2012/03/28
-
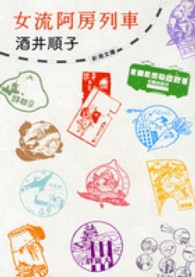
- 和書
- 女流阿房列車 新潮文庫