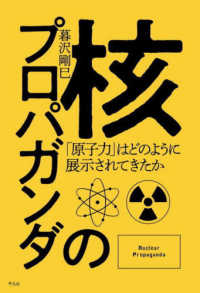内容説明
近世初頭、物資の大量輸送の目的で各地に川の港=河岸が設けられ、物流のターミナルとして賑わった。利根川水系を中心に、河岸に生きる人々の暮らしの足跡を辿ってその盛衰を描き、忘れられた河岸水運の時代の生活の息吹を蘇らせる。
目次
第1章 「河岸」とは何か
第2章 河岸のなりたち
第3章 河岸と湊
第4章 江戸の河岸
第5章 河岸の構成
第6章 河岸の生態
第7章 うごめく河岸
第8章 河岸の衰退
著者等紹介
川名登[カワナノボル]
1934年千葉県生まれ、千葉大学文理学部卒業。明治大学大学院博士課程満期退学。千葉経済大学名誉教授、文学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
76
河岸を「かし」と読むと答えた人は1割という。 機能を川の湊(みなと)と答えた人はその半分。 利根川水系では郷土学習で教えているとのこと。 船の持つ低公害,低燃費,大地震等災害時での強さから,水運の復活を著者は感じている2012/08/22
kenitirokikuti
5
図書館にて。著者は千葉経済大学の名誉教授。著書に『近世日本水運史の研究』など▲東廻航路は東北諸藩の江戸廻米によって始まった。この観点を取ると、利根川東遷も同じだな。本書、銚子・佐原・木下(きおろし)・境について個別記述がある。昭和30年代まで、国鉄佐原駅では利根川を上って船で運ばれてきた米俵を貨車に積み替えていたそうな。コンテナトラックがそれを終わらせた▲第七章 うごめく河岸/遊郭盛衰記。潮来節「いたこ出島のまこもの中にあやめ咲くとはつゆしらず」船女房、廻船洗濯宿から遊郭になるところも。2023/04/20
メルセ・ひすい
1
9-32 車と道路がなくて大量輸送・・ 水運デスヨネ・・ 近世初頭、年貢米や商品の大量輸送の目的で各地に水運路が開かれ、川の港として河岸が設けられた。利根川水系を中心に、河岸に生きる人々の暮らしの足跡を辿ってその盛衰を描き、河川水運の未来を展望する。2007/11/06
-
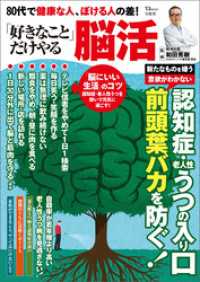
- 電子書籍
- 80代で健康な人、ぼける人の差! 「好…