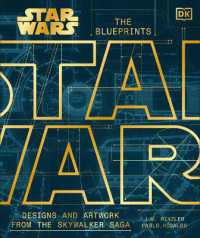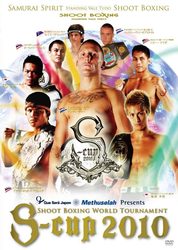出版社内容情報
古代エジプトのセネト,ヨーロッパのバクギャモン,中近東のナルド,中国の双陸などの系譜に日本の盤雙六を位置づけ,遊戯・賭博としてのその数奇なる運命を辿る。
内容説明
盤すごろくの数奇なる運命を世界史的に追う。古代エジプトのセネトに遡る競走ゲームの系譜に日本の盤すごろくを位置づけ、中・近世における大流行から近・現代の衰退まで、その運命を語る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
わ!
1
以前の大河ドラマ「平清盛」では、主人公清盛と、後白河院がよく雙六をしていた。この場合の「すごろく」は盤雙六、本雙六といわれるもので、「雙六」と書き表し、この後江戸時代になって、私たちが今でもサイコロを振って楽しむ絵双六が登場する。この絵双六は「双六」と書き表すのが増川さんのルールのようです。 この「ものと人間の文化史」シリーズの「すごろく」は、「1」が「雙六」を「2」が「双六」の説明となっています。 一つのモノを掘り下げると、ここまで楽しめるのか…と驚かされる本ですね。2021/12/10
砂
1
Ⅰの方は絵の描かれたこまの上を、さいころの目に従って進んでいく「絵双六」ではなく、盤とさいころをつかった「雙六」(≒バックギャモン)について。その歴史や、変遷などの記述も素晴らしいが、第四章で増川氏が提唱する「ゲームの法則」(進化性・伝播性・実践性・民族性・階級性・賭博性)が興味深い。今日的なデジタルゲームを考える上で、どのようにこれが論じられるのかなどを考えてみたい。2014/09/23