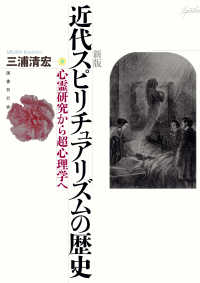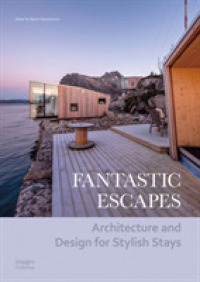出版社内容情報
英米系の分析哲学と大陸系の政治哲学・社会哲学を架橋し、観念論を中心に哲学史を刷新して、理論と実践の新たな関係へと光をあてる。ハーバーマスが哲学史と対峙する。英米系の分析哲学と、大陸系の政治哲学や社会哲学という大きな二つの流れが架橋可能であることを明快に示す。ローティ、ブランダム、パトナム、フンボルト、ヘーゲル、カントなどを言語論的カント主義の流れをくむプラグマティズム的認識実在論において論じ、ドイツ観念論を分析哲学の用語で書き換える。哲学史からさらには理論と実践の関係へ、新たな光をあてる。
序論 語用論的転回後の実在論
??第一節 コミュニケーションか、叙述か?
??第二節 内容とテーマ設定
??第三節 超越論的な問題設定──プラグマティズム以後のゆくえ
??第四節 結果として生じるふたつの問題──認識の客観性が脅かされ、世界と世界内的なものとの差異が消し去られること
??第五節 弱い自然主義──カントとダーウィン以後
??第六節 鏡像論をともなわない実在論
??第七節 真理と正当化
??第八節 合法性における進歩
第一部 解釈学から形式語用論へ
第一章 解釈学的哲学と分析哲学──言語論的転回のふたつの相互補完的バージョンについて
??第一節
??第二節
??第三節
第二章 相互了解の合理性──コミュニケーション的合理性という概念に関するスピーチアクト理論からの解説
??第一節 合理性の三つの根
??第二節 言語使用の様相
??第三節 コミュニケーション的行為対戦略的行為
??第四節 コミュニケーション的合理性と言語による世界開示
??第五節 付論 語用論的意味理論
第二部 間主観性と客観性
第三章 カントからヘーゲルへ──ロバート・ブランダムの言語語用論
??第一節
??第二節
??第三節
??第四節
??第五節
??第六節
第四章 脱超越論化の道──カントからヘーゲルへ、そしてヘーゲルからカントへ
??第一節
??第二節
??第三節
??第四節
??第五節
第三部 ディスクルスと生活世界における真理
第五章 真理と正当化──リチャード・ローティの語用論的転回
??第一節 プラトン主義的衝動に駆られた反プラトン主義者
??第二節 語用論的転回
??第三節 パラダイム固有の問題としてのコンテクスト主義と懐疑主義
??第四節 真理と正当化
??第五節 意味論的な真理概念と語用論的パースペクティヴ
??第六節 語用論的パースペクティヴから見た認識論的真理概念
??第七節 語用論的な真理概念
??第八節 言語化された理性の自然化
第六章 価値と規範──ヒラリー・パトナムのカント的プラグマティズムへの注釈
??第一節
??第二節
第七章 「正当性」対「真理」──道徳的な判断と規範が当為として妥当することの意味について
??第一節
??第二節
??第三節
??第四節
??第五節
??第六節
??第七節
??第八節
第四部 哲学の限界
第八章 再び、理論と実践の関係について
訳者解説
訳者あとがき
人名索引
ユルゲン・ハーバーマス[ハーバーマス ユルゲン]
(J?rgen Habermas)
1929年ドイツのデュッセルドルフ生まれ。ゲッティンゲン,チューリヒ,ボンの各大学でドイツ文学,心理学,社会学,哲学を修め,56年フランクフルト社会研究所のアドルノの助手となり,フランクフルト学派第二世代としての歩みを始める。61年『公共性の構造転換』で教授資格を取得し,ハイデルベルク大学教授となる。64年フランクフルト大学教授,71年マックス・プランク研究所所長を歴任,82年以降はフランクフルト大学に戻り,ホルクハイマー記念講座教授を務め,94年退官。60年代末のガダマーらとの解釈学論争,ルーマンとの社会システム論争,さらに『コミュニケーション的行為の理論』(81)をはじめとする精力的な仕事,86年の歴史家論争以降の多方面にわたる社会的・政治的発言を通じて,ドイツ思想界をリードし,国際的にも大きな影響を与えてきた。2004 年11月には「京都賞」を受賞。主な著書に,『近代の哲学的ディスクルス』(85),『遅ればせの革命』(90),『討議倫理*』(91),『事実性と妥当性』(92),『他者の受容*』(96),『人間の将来とバイオエシックス*…
三島 憲一[ミシマ ケンイチ]
1942年生まれ。大阪大学名誉教授。専攻:社会哲学・ドイツ思想史。著書:『ベンヤミン──破壊・収集・記憶』(講談社学術文庫),『歴史意識の断層──理性批判と批判的理性のあいだ』『ニーチェ以後──思想史の呪縛を越えて』(以上,岩波書店),訳書:ハーバーマス『人間の将来とバイオエシックス』(法政大学出版局),レーヴィット『ヘーゲルからニーチェへ──十九世紀思想における革命的断絶(上下)』(岩波文庫)など。
大竹 弘二[オオタケ コウジ]
1974年生まれ。南山大学外国語学部ドイツ学科准教授。専攻:現代ドイツ政治理論・政治思想史。著書:『正戦と内戦──カール・シュミットの国際秩序思想』(以文社),『統治新論──民主主義のマネジメント』(共著,太田出版),訳書:デュットマン『思惟の記憶──ハイデガーとアドルノについての試論』(月曜社)同『友愛と敵対──絶対的なものの政治学』(共訳,月曜社)など。
木前 利秋[キマエ トシアキ]
1951年生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科教授。専攻:社会思想・現代社会論・フランクフルト学派・批判理論。著書:『理性の行方──ハーバーマスと批判理論』『メタ構想力──ヴィーコ・マルクス・アーレント』(以上,未來社)。『ハーバーマスと現代』(共編,新評論)『葛藤するシティズンシップ──権利と政治』『変容するシティズンシップ──境界をめぐる政治』(以上,共編,白澤社)など。2013 年12 月逝去。
鈴木 直[スズキ タダシ]
1949年生まれ。東京経済大学経済学部教授。専攻:ドイツ思想史。著書:『マルクス思想の核心──21世紀の社会理論のために』(NHK出版),『輸入学問の功罪──この翻訳わかりますか?』(ちくま新書),訳書:ハーバーマス『ああ,ヨーロッパ』(共訳,岩波書店),同『引き裂かれた西洋』(共訳,法政大学出版局),シュトレーク『時間かせぎの資本主義──いつまで危機を先送りできるか』(みすず書房)など。
内容説明
哲学の限界を超えて。ローティ、ブランダム、パトナム、ヘーゲル、カントなどを言語論的カント主義の流れをくむプラグマティズム的認識実在論において論じ、ドイツ観念論を分析哲学の用語で書き換え、英米系の分析哲学と、大陸系の政治哲学や社会哲学という大きな二つの流れが架橋可能であることを明快に示す。哲学史を刷新し、理論と実践の関係に、新たな展望をもたらす。
目次
語用論的転回後の実在論
第1部 解釈学から形式語用論へ(解釈学的哲学と分析哲学―言語論的転回のふたつの相互補完的バージョンについて;相互了解の合理性―コミュニケーション的合理性という概念に関するスピーチアクト理論からの解説)
第2部 間主観性と客観性(カントからヘーゲルへ―ロバート・ブランダムの言語語用論;脱超越論化の道―カントからヘーゲルへ、そしてヘーゲルからカントへ)
第3部 ディスクルスと生活世界における真理(真理と正当化―リチャード・ローティの語用論的転回;価値と規範―ヒラリー・パトナムのカント的プラグマティズムへの注釈;「正当性」対「真理」―道徳的な判断と規範が当為として妥当することの意味について)
第4部 哲学の限界(再び、理論と実践の関係について)
著者等紹介
ハーバーマス,ユルゲン[ハーバーマス,ユルゲン] [Habermas,J¨urgen]
1929年ドイツのデュッセルドルフ生まれ。ゲッティンゲン、チューリヒ、ボンの各大学でドイツ文学、心理学、社会学、哲学を修め、56年フランクフルト社会研究所のアドルノの助手となり、フランクフルト学派第二世代としての歩みを始める。61年『公共性の構造転換』で教授資格を取得し、ハイデルベルク大学教授となる。64年フランクフルト大学教授、71年マックス・プランク研究所所長を歴任、82年以降はフランクフルト大学に戻り、ホルクハイマー記念講座教授を務め、94年退官
三島憲一[ミシマケンイチ]
1942年生まれ。大阪大学名誉教授。専攻:社会哲学・ドイツ思想史
大竹弘二[オオタケコウジ]
1974年生まれ。南山大学外国語学部ドイツ学科准教授。専攻:現代ドイツ政治理論・政治思想史
木前利秋[キマエトシアキ]
1951年生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科教授。専攻:社会思想・現代社会論・フランクフルト学派・批判理論。2013年12月逝去
鈴木直[スズキタダシ]
1949年生まれ。東京経済大学経済学部教授。専攻:ドイツ思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
34