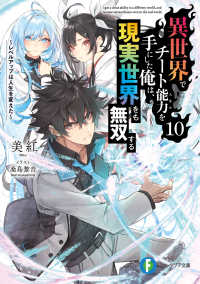内容説明
近世中期、上方学芸の隆盛の背景には、豊富に舶載受容された明清漢籍の存在があった。儒学はもとより医学、書学、そして国学(和学)においても、漢学の日本文化に与えた影響は大きく、それは大名家、富裕層、さらには新興の個人蔵書家の蔵書や漢籍の要文を書き抜き、手控えとした抄記などにまざまざと表れている。都賀庭鐘『過目抄』、奥田尚斎『拙古堂日纂』などの漢籍抄録、漢籍・和刻本における書入など、諸種の読書記録を詳細に分析。さらには文学・書画・医学など多方面に大きな影響を与えた『世説新語補』の受容の諸相を把捉することで、漢籍受容の諸相を鑑に近世中期日本の特質を明らかにする画期的著作。
目次
第1部(上方の学芸と明清漢籍;『拙古堂日纂』における明清書学書;上方における儒者の身分と職分 ほか)
第2部(都賀庭鐘『過目抄』考;上田秋成『山〓(やまづと)』考
上田秋成の日本古典学と中国学 ほか)
付録(『拙古堂日纂』・『拙古堂雑抄』の抄出書目並びに注記;『蜀素帖(米南宮自書詩巻真蹟)』題跋一覧
佐野市郷土博物館須永文庫本『米南宮自書詩巻真蹟』書影)
著者等紹介
稲田篤信[イナダアツノブ]
1947年生まれ。東京都立大学(首都大学東京)名誉教授、元二松学舎大学特別招聘教授。専門は日本近世文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
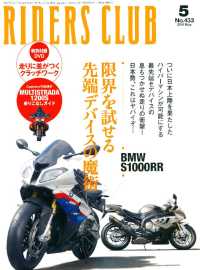
- 電子書籍
- RIDERS CLUB No.433 …