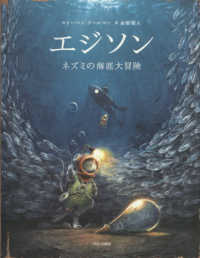内容説明
古来、絵画は、ひとつ鑑賞の目的のみならず、そこに描かれた題材や物語から、あるべき生き方、倣うべき考え方を学び、自らを顧みるための装置として存在していた。特に東アジアにおいては、中国を淵源とする儒教思想に基づき、善行を勧め、悪行を戒めるために描かれた『勧戒画』がひろく作成され、それらは、いまなお各地に多種多様な作品として伝存している。人びとの思想や生活に対し、絵画はどのように機能し、展開していったのか―古代から近代における『勧戒画』の諸相を多角的に考察、作品が生まれ、受容された時代の思想・文化を捉えなおすとともに、時代を超えて、見る者の「鑑」となる美術作品の力を再認識する刺激的な一冊。
目次
1部 勧戒画の成立(勧戒のシンボル―礼拝空間における孔子祭祀のあり方;漢代画像石にみる儒教的モチーフ―墓域という空間におけるその機能 ほか)
2部 勧戒画の題材(玄宗皇帝絵にみる勧戒性―長恨歌絵を中心に;王昭君図―勧戒画への発展 ほか)
3部 帝王学の書と絵―帝鑑図(万暦帯、張居正と『帝鑑図説』;「帝鑑図」の変遷―青蓮院・名古屋城・熊本城の障壁画と仙台藩の事例から ほか)
4部 勧戒画を使った人と空間(宋代皇帝と勧戒の空間―「無逸図」と「山水図」;「荘厳」する瑞獣―将軍家光の先祖祭祀における勧戒画 ほか)