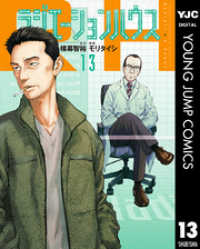内容説明
近世~近代初期、書籍はどのように人々の手に届いたのか。貸本屋や絵草紙屋、小間物屋等の営業文書や蔵書書目・看板・仕入れ印など、書籍流通の実態を伝える諸史料を「眼光表紙裏に徹する」博捜により再構築し、書籍文化史の動態を捉える。
目次
第一部 書籍流通史研究の意義と方法(出版とは何か―開版を促す原動力としての流通;書籍流通史研究の意義と方法、その資料)
第二部 書籍流通のさまざま、史料のさまざま(仕入印と符牒;近世日本における薬品・小間物の流通と書籍の流通;店頭の書籍広告―「看板」小考;近世日本における大般若経流通の一相;京都の絵草紙屋和久谷治兵衛・桜井屋治兵衛;『戊辰以来 新刻書誌便覧』の諸本)
第三部 貸本という書籍流通(貸本屋の営業文書;貸本屋沼田屋徳兵衛の営業文書;信州諏訪升屋文五郎の貸本書目)
著者等紹介
鈴木俊幸[スズキトシユキ]
中央大学文学部教授。専門は書籍文化史、日本近世文学研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。