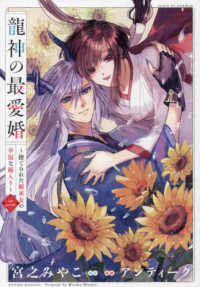内容説明
権力に対峙した人びとは如何にしたたかに生き抜いたのか―。中世日本、村に生きた人びとは、権力の支配に接触、抵触しつつ、それぞれの選択と行動をもって、生存の在り方を模索していた。残された史料を丁寧に読み込むことにより、地に足をつけ、働き廻る、活きるためには戦もいとわない普通の住民たちの動態的な歴史社会像を描き出す。
目次
序論 日本中世村研究の逍径
1 村の実像をもとめて(鎌倉期「百姓中」の出現;中世利根川の築堤と堤用途―「万福寺百姓等申状」の検討;戦国期の仏神田と領主・地下―越前国池田荘を事例として ほか)
2 領主支配と村の動向(摂関家領近江国信楽荘における領域と村落;室町期守護権力による軍役・陣夫役の賦課―播磨国矢野荘を事例として;室町末期武家領主による所領支配の実態―長尾忠景を事例に)
3 境界と村の力(村の自立と紛争・内乱―紀伊国三上荘願成寺と西畑村;中近世移行期の浅利氏と比内の村々―陸奥・出羽国境の境目争い;近世初期領国境目地域における庄屋と百姓鉄炮)
著者等紹介
蔵持重裕[クラモチシゲヒロ]
立教大学名誉教授。専門は日本中世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。