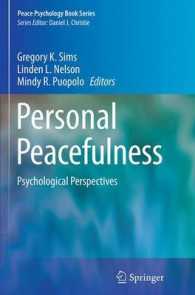内容説明
和歌の史的蓄積を自らの歌学の中に位置づけ、後の和歌と勅撰集のあり方を方向づけた俊成や定家。彼らの和歌観を直接・間接に選択・継承し、それぞれの和歌のあり方を模索していった為家や京極派。王朝和歌から連なる中世和歌の史的変遷を丁寧に紐解き、個々の特質と連続性を多面的に明らかにする待望の一書。
目次
序論(中古「本歌取」言説史論;本歌取説と実作の評価―定家の所説と秀歌撰歌をめぐって;古注の言説と和歌の実作と現代の注釈と―「括る」か「潜る」か;作意と解釈―『新古今集』の羈旅歌二首をめぐって)
歌学論(『新勅撰和歌集』序の理念;『詠歌一体』論;『遂加』の方法;『越部禅尼消息』論)
表現論(中世和歌表現史論;『土佐日記』の和歌の踪跡;「空に知る」考;「身を身」と「思ふ」考)
京極派和歌各論(「けしき」の様相;「三日月」をよむ;“軒”をとおして;“間”にうかがう)
歌人論(西行の影響―『十訓抄』と関東歌人に見る;臨終の俊成―「普賢品」を覚悟すること;妻の死・母の死―俊成・定家と『源氏物語』;治世の音・亡国の音―定家とその周辺)
著者等紹介
中川博夫[ナカガワヒロオ]
1956年生まれ。鶴見大学文学部教授。博士(文学)。専門は和歌文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
吉田裕子
0
少々読み辛い論文集。序言より「中古のいわゆる王朝和歌から中世和歌への転換は、和歌に歴史があることを自覚した『千載和歌集』、王朝和歌の亀鑑『古今和歌集』を古典として新たに捉え返した『新古今和歌集』、八代集全体を反省的に概括して新たに歩を進めた『新勅撰和歌集』、の三集を通じて、緩やかにしかし確かに成し遂げられたよつに見える。そこには藤原俊成・定家父子が大きく関わっている。俊成は、絶対的古典としての『古今集』を発見して三代集を古典の基盤と見定め、『後拾遺和歌集』を和歌史の屈折点と捉えた。それを定家は受け継いだ」2021/05/01
-

- 和書
- 実録女師