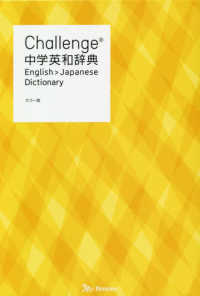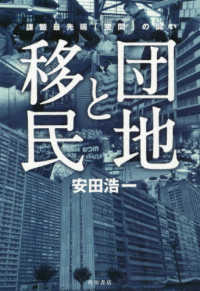内容説明
人間の生と死を探求した“物語”の一大原点―仏教の創始と展開とともに、アジア各地に広まり、地域や時代ごとに多種多彩な再創造を繰り返し、受け継がれてきた仏伝文学。古代のみならず中世から近現代まで幅広く、その展開を捉え、中国、朝鮮半島、日本、ベトナムなど、東アジアの漢字漢文文化圏に共有された文化・文学の意義を検証する。
目次
1 東アジアの“仏伝文学”(日本と東アジアの“仏伝文学”;仏伝文学に見えるエロティックな記述を中国人はどう受け止めたか―Buddhacarita(仏所行讃)の漢訳が示すもの ほか)
2 中国の“仏伝文学”(王勃『釈迦如来成道記』研究序説;敦煌と仏伝文学 ほか)
3 朝鮮半島の“仏伝文学”(韓日における「仏伝」の展開―釈迦と耶輸陀羅の関係を中心に;仏伝の「降魔成道」にみる魔王親子の葛藤 ほか)
4 ベトナムの“仏伝文学”(ベトナムの前近代における釈迦の伝記について―『如来応現図』を中心に;「徐道行大聖事跡實録」をめぐって ほか)
5 日本の“仏伝文学”(出家譚と妻と子と―仏伝の日本化と中世説話の形象をめぐって;『釈迦の本地』とその展開―涅槃の場面を端緒として ほか)
6 “仏伝文学”とその周辺(仏伝図の展開―宗教美術:伝記図の機能;龍女と仏陀―「平家納経」提婆品見返絵の解明をめざして ほか)
著者等紹介
小峯和明[コミネカズアキ]
1947年生まれ。中国人民大学高端外国専家、立教大学名誉教授、フェリス女学院大学客員教授、早稲田大学客員上級研究員、放送大学客員教授。文学博士。専門は日本中世文学、東アジアの比較説話(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。