内容説明
文字文芸の基盤には、文字にならない口承の言語伝承が確実に存在している。そして説話には、その表現を根底から支える原理的な枠組みがある。「文献そのものの解明」から脱却し、相互の影響関係や受容関係に捕らわれず「話型」・「表現」に着目することにより、地域的な文化や歴史の異なりなどが織り重なる説話の深層に踏み込む。説話を「立体的」に捉えるための方法論。
目次
1 伝承的表現論(なぜ昔話が、なのか;昔話の分類とは何か ほか)
2 比較という方法―口承・書承と日韓比較(比較とは何か;昔話「継子虐め」の日韓比較 ほか)
3 昔話と説話とに共有される話型(『宇治拾遺物語』の中の昔話;『宇治拾遺物語』第三話と昔話「瘤取爺」―構造からと、表現からと ほか)
4 『宇治拾遺物語』説話の個別性(「平安京の物語」としての『宇治拾遺物語』;規範と逸脱 第七六話「仮名暦誂タル事」 ほか)
著者等紹介
廣田收[ヒロタオサム]
1949年大阪府豊中市生まれ。1973年3月同志社大学文学部国文学専攻卒業。1976年3月同志社大学大学院文学研究科国文学専攻修士課程修了。専攻・学位、古代・中世の物語・説話の研究、博士(国文学)。現職、同志社大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
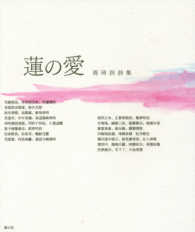
- 和書
- 蓮の愛周〓詞詩集





