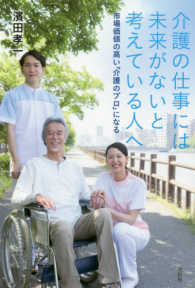出版社内容情報
ことばの多様性と流動性が織りなす日本語変遷史「品詞のハキダメ」「落ちこぼれ」などと表現され、品詞分類においてネガティブなものとして位置づけられてきた副詞。
しかし、本当に副詞は分類も体系化もし難い存在なのであろうか。
古代語から近代語への転換期における程度副詞の流動的な性質を捉え、時代別の共時的な分類体系を横糸に、特徴的な語の通時的な変化を縦糸として交差させることで、ことばの意味・機能の体系的な変遷の模様を描き出す。
はしがき
序 章 副詞研究の流れと程度副詞体系
? 古代語から近代語へ─高程度を表す副詞の体系の変遷―
第一章 評価的な程度副詞の成立と展開
第二章 高程度を表す副詞の体系変遷概観
? 過渡期の諸相・一─評価的な程度副詞を中心とした体系の成立背景─
第三章 中世後期から近世初頭の高程度を表す副詞の体系
第四章 成立過程から見た高程度を表す評価的な程度副詞の特徴─「チカゴロ」を例として─
第五章 古語と口語のはざまにある『天草版平家物語』の語法─「コトノホカ」「モッテノホカ」の用法をめぐって─
? 過渡期の諸相・二─高程度を表す評価的な程度副詞の特徴─
第六章 古代語近代語過渡期の代表的な高程度を表す副詞「アマリ(ニ)」
第七章 感動詞・応答詞と評価的な程度副詞との連続性─大蔵虎明本における「ナカナカ」の分析を中心に─
? 現代語への一歩─高程度を表す副詞の二系統化─
第八章 近世前期上方語における高程度を表す副詞の体系
第九章 〈程度の甚だしさ〉と〈多量〉を表す近世前期上方語の「タント」
まとめ
引用参考文献/既発表論文と章との関係
あとがき/索引(事項・語句・資料名)
田和真紀子[タワ マキコ]
清泉女子大学准教授。専門は日本語史。博士(文学)。
研究テーマとして、日本語の語彙・意味の変化に興味を持っている。その中でも、特に意味・機能の変化が激しい副詞に興味を持ち、現在も研究を続けている。また近年は、一単語レベルの意味・機能の変化や歴史だけでなく、語彙・品詞レベルでの歴史的な変化の傾向に注目している。
内容説明
「品詞のハキダメ」「落ちこぼれ」などと表現され、品詞分類においてネガティブなものとして位置づけられてきた副詞。しかし、本当に副詞は分類も体系化もし難い存在なのであろうか。古代語から近代語への転換期における程度副詞の流動的な性質を捉え、時代別の共時的な分類体系を横糸に、特徴的な語の通時的な変化を縦糸として交差させることで、ことばの意味・機能の体系的な変遷の模様を描き出す。
目次
副詞研究の流れと程度副詞体系
1 古代語から近代語へ―高程度を表す副詞の体系の変遷(評価的な程度副詞の成立と展開;高程度を表す副詞の体系変遷概観)
2 過渡期の諸相・一―評価的な程度副詞を中心とした体系の成立背景(中世後期から近世初頭の高程度を表す副詞の体系;成立過程から見た高程度を表す評価的な程度副詞の特徴―「チカゴロ」を例として;古語と口語のはざまにある『天草版平家物語』の語法―「コトノホカ」と「モッテノホカ」の用法をめぐって)
3 過渡期の諸相・二―高程度を表す評価的な程度副詞の特徴(古代語近代語過渡期の代表的な高程度を表す副詞「アマリ(ニ)」
感動詞・応答詞と評価的な程度副詞との連続性―大蔵虎明本における「ナカナカ」の分析を中心に)
4 現代語への一歩―高程度を表す副詞の二系統化(近世前期上方語における高程度を表す副詞の体系;“程度の甚だしさ”と“多量”を表す近世前期上方語の「タント」)
著者等紹介
田和真紀子[タワマキコ]
東京都立大学大学院人文科学研究科国文学専攻博士課程修了、博士(文学)。宇都宮大学教育学部専任講師、同准教授を経て、清泉女子大学准教授。専門は日本語史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。