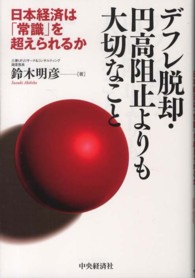出版社内容情報
書く、包む、飾る、補う…古来、日本人の生活のなかに紙は常に存在していた。
時代の美意識や技術を反映しながら、さまざまな用途に合わせ、紙は作られ、選ばれ、利用されていた。
長年文化財を取り扱ってきた最先端の現場での知見を活かし、さまざまな古典作品や絵巻物をひもときながら、文化の源泉としての紙の実像、そして、それに向き合ってきた人びとの営みを探る。
カラー口絵
はじめに
一 紙漉き
一 絵巻物にみる紙漉き
二 職人歌合にみる紙漉き
三 古典文学にみる紙漉き
1 都での紙漉き
2 地方での紙漉き
3 寺院と紙漉き
四 『紙漉重宝記』にみる紙漉き
二 紙の機能と用途
一 書く(書写・記録材)
1 紙の取捨選択
2 扇と色紙
3 香染紙
4 扇面と文字・歌絵
5 様々な文字
6 白き色紙と色紙形
7 重紙
8 紙面と筆
9 版本の紙
二 包む
1 包み紙
2 陸奥紙と檀紙
3 紙屋紙
4 畳紙と懐紙
5 薬袋紙
6 懐紙
7 裹紙
8 その他
三 飾る
1 色紙と襲色
2 御幣と紙垂
3 能紙
4 紙人形
四 補う(補修紙)
1 障子と美濃紙
2 繕う(修理)
五 着る、かぶる(衣服)
1 紙衣
2 紙衾
3 紙冠と巾子紙
4 雨衣と唐傘
六 結ぶ、付ける
1 陸奥紙と薄様
2 色紙
3 紙屋紙と重紙
4 元結と紙縒
5 物忌札と短冊
七 拭く、撫でる
1 鼻紙
2 顔拭き
八 隠す
九 隔てる、敷く
1 間を隔てる紙
2 ものを敷く紙
十 張る
1 扇と団扇
2 板張り
3 燈籠
十一 紙に係わる職人と仕立
1 紙に係わる職人
2 仕立ての方法
3 封式
三 紙名と紙色
一 紙名
1 紙名と原料
2 地方産の紙名
3 品質と規格
4 よく見る紙名
二 紙色
1 紅紙と紫紙
2 薄様と襲色
3 黄紙
4 紺紙と藍紙
5 色紙
6 装飾紙
三 鳥の子と厚紙
四 唐紙と空紙
四 反古紙
一 奈良時代の反古紙
二 平安時代の反古紙
三 中世の反古紙
四 漉き返し紙
五 鈍色紙
おわりに
注釈
池田寿[イケダ ヒトシ]
1957年生まれ。文化庁文化財部美術学芸課主任文化財調査官。専門は日本中世史。
著書に『日本の美術 第480号 書跡・典籍、古文書の修理』(至文堂、2006年)、『日本の美術 第503号 武人の書』(至文堂、2008年)などがある。
内容説明
古来、日本人の生活のなかに紙は常に存在していた。時代の美意識や技術を反映しながら、さまざまな用途に合わせ、紙は作られ、選ばれ、利用されていた。長年文化財を取り扱ってきた最先端の現場での知見を活かし、さまざまな古典作品や絵巻物をひもときながら、文化の源泉としての紙の実像、そして、それに向き合ってきた人びとの営みを探る。
目次
1 紙漉き(絵巻物にみる紙漉き;職人歌合にみる紙漉き ほか)
2 紙の機能と用途(書く(書写・記録材)
包む ほか)
3 紙名と紙色(紙名;紙色 ほか)
4 反古紙(奈良時代の反古紙;平安時代の反古紙 ほか)
著者等紹介
池田寿[イケダヒトシ]
昭和32(1957)年生まれ。文化庁文化財部美術学芸課主任文化財調査官。専門は日本中世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
きくち
R
-

- 電子書籍
- 女神育成システム【タテヨミ】第250話…
-

- 和書
- すべての人の天文学