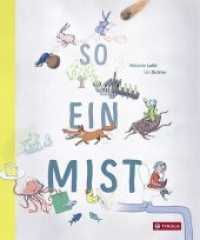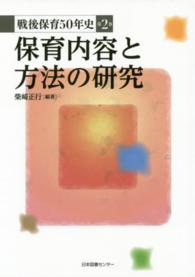目次
第1章 研究の自立に向けて(近代文学研究の胎動;「世代の相剋」について ほか)
第2章 「文学史」を求めて(反近代;文学史研究のアポリア ほか)
第3章 「作品論」の射程(作品の内部表徴を追って;作家研究のグルント ほか)
第4章 「作者」とは何か(作家論の形の批評;作家論のアポリア ほか)
第5章 研究の多様化の中で(無暗にカタカナに平伏する癖;文学研究の十年 ほか)
著者等紹介
三好行雄[ミヨシユキオ]
1926年1月2日、福岡県生まれ。50年、東京大学文学部国文学科卒業。共立女子短期大学(55~59年)、立教大学(59~62年)、東京大学(62~86年)、大妻女子大学(86~90年)、昭和女子大学(90年)に専任教員として勤務。90年には、山梨県立文学館初代館長となる。1990年5月20日、死去。享年64
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きつね
7
「卒論はテクスト論?あ、そう……」テクスト論と作品論を二項対立で考えている人は読んだ方が良い。だいたい、テクスト論の手引きほど茫漠としたものはない。 作品論の提唱者と「されてしまった」三好氏は1962年東大国文科初の近代文学専攻教官。好事家の「鑑賞」やスター批評家たち(平野謙、荒正人から江藤淳、蓮實重彦…)の「批評」から「研究」を自立させようと苦心された方。既に著作集が編まれているが本書は「文学史」「作品論」「作家論」などテーマ別に初期から晩年までの記事が編まれており、よい手引きになるかと思う。 以下引用2012/04/30
悸村成一
0
やっぱり気ままな読書が一番愉しいし、確実に楽。図書館本。 1122014/12/13
-
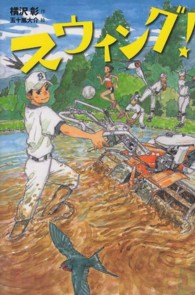
- 和書
- スウィング!