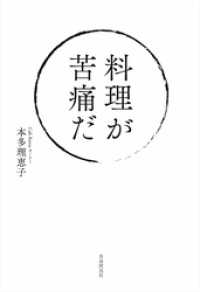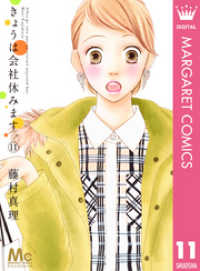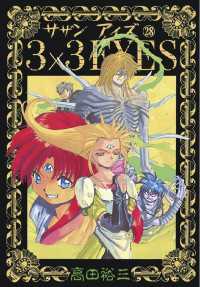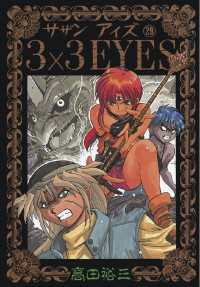内容説明
SNSの登場で、一億総政治評論家と呼べる事態が出来した。しかし、ネットの言論空間は、現実政治からは遊離している。ユーザーは偽りの万能感に浸りながら、ことさら極端な主張に走る。その結果、本来、自分たちが実現したかったことも実現できなくなる。私たちはいまこそ気づかねばならない。自由な思いの丈を表現していると私たちが感じているネットの言論空間は、実は、何者かによってコントロールされているのではないのか、と。
目次
プロローグ―「ネット右翼」の台頭する震災後の日本
第1章 いまさらの「歴史認識問題」に揺れる二〇一〇年代ニッポン
第2章 朝日新聞を叩きすぎて自滅するメディア
第3章 再稼働反対デモこそが脱原発の阻害要因
第4章 それは誰にとっての利益なのか(qui bono)
第5章 騙されない思考を身に着ける
第6章 政治の現場とネット言論の距離を詰める作業を
著者等紹介
中田安彦[ナカタヤスヒコ]
1976年、新潟県生まれ。早稲田大学社会科学部卒業。大手新聞社に一時勤務後、副島国家戦略研究所(SNSI)にて研究員として活動。アメリカの政治思想、対日戦略のほか、欧米の超財界人など、世界を動かす企業・人的ネットワークを主な研究テーマとする(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
30
一見オープンだと錯覚するネット上での言説は、気づくと偏った極論ばかりの閉鎖空間。匿名の場所であえて不快な言葉に近づく必要などなく、気づけば周りは同種の言葉、そこでさらに承認されたいなら…。確かに、必然だ。◇ネトウヨなら「日本を滅ぼす」のはネトサヨと思ったろうし、逆もまた真。反知性に走る両者にともに歯止めをかけようと中田が起用したのが、共通の敵たりうるアメリカのジャパンハンドラーズ。政治的には陰謀にすらあたらぬ当然のことだろうが、一人でも端っこから引きはがせたら確かに成功だ。陰謀関連の語彙もそのためにある。2015/04/20
Honey
10
ネットで情報に接することの、著者の体験と反省を交えた警告。 具体的な例話に関しては、まぁ今更、とか、ちょっと冗長におもえたり、必ずしも同意しないところもあったので、途中から斜め読み。 ですが、今や大変重宝なツールであるネット。煽動に乗せられたり利用されたりすることなく、発信者の意図や背景にも留意して、上手に活用しましょう、本も読みましょう、というよいメッセージだと思います。 2019/08/06
西澤 隆
8
ネット上の議論が簡単に煽られてカタルシスのためのものとして先鋭化し、結果として問題解決をより遠ざけるというのはここのところずっと自分も感じていること。そういう意味では目次を読むととても共感できる本なのだが読み進めていくと「これもまたちがった形の煽りだな」と実感する手触りでもあった。熟語に英語の言葉でルビを振るやり方を多用するひとは、往々にして相手になにかを穏やかに伝えようとはしておらず「位攻め」的に力で説き伏せてしまおうとしているか煙に巻こうとしていることが多い。これも「コンサルタントの芸」だな(笑)。2015/04/25
ネギっ子gen
6
ネトウヨ第1世代だった著者による警世の書。【評価の高い箇所】180頁。原子力業界文書に<「美味しん坊」というシリーズマンガはストーリーもあるし、料理の中身についてもよく解説している。あの手口に学びたい>との記述があると。敵もさるものです。「坊」は愛嬌だが。さらに、<ヒロセタカシ現象についてもしているしっかり研究して、対応策を備えて>いたとして、<それに対して、いまの福島原発事故を受けて活動している反原発派は、自らの「敵」の弱みをどれだけ効果的に突いているのか、わたしは疑問に思います>と書く。全く同感です。2019/11/03
Aby
6
「ネット世論」は極論に走りがちで,何を実現するのか/したいのかを見失いがち.ネット世論:自分が見ている世界がすべてではない,ということの自覚が欲しい.というのは「何でも知っていると思うなよ」の繰り返しか.その自覚があるだけでも随分と違うのだと思う.……最後の方は,うーん,なくてもいいような.2015/08/18