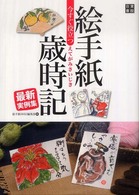内容説明
原風景、信州には、様々な歴史ロマンが潜んでいた!安曇族をはじめ、諏訪大社、真田一族、善光信の謎を追う!地名の由来シリーズ第五弾。写真・周辺地図・折り込みマップつき。
目次
第1章 「故郷」の“ふるさと”信州
第2章 地名で追う諏訪一族の謎
第3章 地名でたどる安曇族の足跡
第4章 地名で追う真田一族の運命
第5章 地名でたどる善光寺のルーツ
第6章 地名伝説の里を往く
第7章 信州の偉人の生地を訪ねる
第8章 ふるさとの地名の由来
著者等紹介
谷川彰英[タニカワアキヒデ]
1945年長野県生まれ。ノンフィクション作家。東京教育大学(現筑波大学)、同大学院博士課程修了。柳田国男研究で博士(教育学)の学位を取得。筑波大学教授、理事・副学長を歴任するも、退職と同時にノンフィクション作家に転身し、第二の人生を歩む。筑波大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
60
2013年刊。著者が執筆している地域別の『地名の由来を歩く』シリーズの一冊。信州に関わる神話や伝説、古今の著名人の足跡や各地域の地名の来歴を述べる。第一章「故郷」の〝ふるさと〟信州では、文部省唱歌「故郷」の作詞者として知られる高野辰之が取り上げられ、「故郷」の歌詞の中に散りばめられた高野の生涯が記されているが、同郷の者として熱い思いが胸に湧いてくる。以下諏訪一族、安曇族、真田一族の紹介に各章が充てられ、それぞれの地名との関わり、歴史などトピック的な面白さも記されている。「諏訪」という地名は、「洲羽・須波」2024/07/12
Hiroki Nishizumi
2
面白かった。著者の郷土愛に満ち溢れていた。2026/01/06
yoneyama
2
長野の地名が河内長野由来とは知らなかったです。 諏訪族、安曇族の由来、大きく知ることとなりました。伊那、木曽、須坂、深志、信濃の名の由来も。やはり信濃は渡来人だらけで、律令制度直前に、命名の由来がありました。木曽が信濃にあとから加わった事も成程。犀川の名は常々筑摩川ではないのかと思って来たのですが、そのあたりももう少し知りたかった。犀龍伝説以前のことが。地名の由来には動かぬ証拠は少ないけれど、様々な説を説得力もって読みたい。佐久間象山、萩原碌山ほか名前しか知らない人のことがスッキリわかりました。2018/12/05
Juichi Oda
1
タイトルから想像したのは地勢学的な理系の内容だったのですが、豈図らんや!文部省唱歌「ふるさと」や「朧月夜」の詞を書いた信州人・高野辰之の物語からはじまり、諏訪一族の話を辿りつつも「諏訪」という地名がわからない、という結論だったり。そうかと思えば、「伊那」は兵庫県の「猪名川」がルーツで、三重県の「員弁」経由だという驚きがあったり・・・なかなかに興味をそそられる文章でいっぱいの新書でした。ますます信州という土地を知りたくなった次第です。2013/11/15
レコバ
1
話のネタに2013/09/20