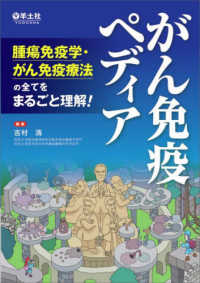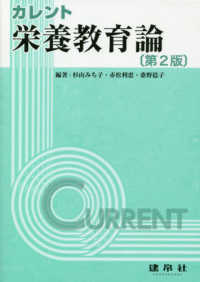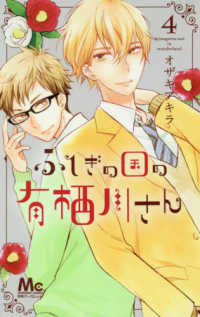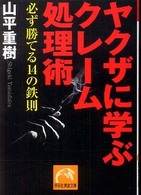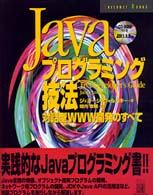内容説明
現代ほどケアの重要性が叫ばれている時代はない。痴呆患者・身障者・ターミナル患者・脳卒中患者・透析患者・病気の子どもたちへの介護や看護の場面で、「ケア」に参加している多くの人たちが直面するマイナスの感情や葛藤はいったい何に起因するのか。ケアする/ケアされる人間関係に精神医学の立場から光をあて、ケアを困難にさせるさまざまな心理的トラブルや精神症状についての正しい理解と現実的な対処の方法を解説する。
目次
第1部 現代のケアとケアの心理―ケアの理論編(ケアの意味を求めて;ケアする側の心理;ケアを受ける側の心理;ケアにおける人間関係)
第2部 精神症状の理解とストレスへの対応―ケアの実践編(ケアの場面でよく出会う精神症状;ケアの対象別に見た心理的問題と対処法;心地よくケアする、心地よくケアを受ける)
著者等紹介
渡辺俊之[ワタナベトシユキ]
1959年群馬県生まれ。1986年東海大学医学部卒業後、東海大学付属病院精神科勤務。現在、東海大学医学部精神科学教室講師、医学博士。精神分析学会認定精神療法医スーパーバイザー。専門は、リエゾン精神医学、精神分析、家族療法、医学教育
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うりぼう
2
ケアする人が、しっかりとケアされていないと、人をケアすることなどできない。2002/07/02
Yasushi I
1
加齢、疾病、障害など様々な場面でのケアについて、ケアをする側、受ける側両方が持つストレス、喜び、学びを丁寧に解説している。たとえ終末期ケアであっても、両者にとって心の成長が続いていく、それがケアの根幹であるという考え方に、一筋の光を見た思いがした。2015/01/23
debehatop
0
ケアをする人・される人、どちらの立場でも否定的感情がわき上がることは避けられないが、それを上手くコントロールしていくことが重要。 両者が知識を持ち、ケアは人格形成の機会と捉えて行動する必要がある。ケアをする対象が誰であろうと、どこであろうとも、相手の成長を助けるという本質があり、それによって自分自身もケアされることになる。 病気や事故だけでなく、人は年を取ると誰もがケアを受ける立場になる。現代は高齢者同士がケアする時代になっており、ストレスを管理して協力者も楽しくケアできる方法を考えることが重要である。2020/01/18