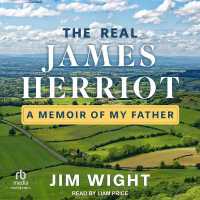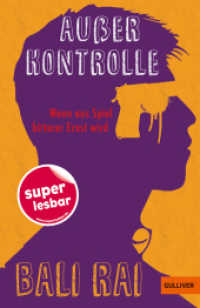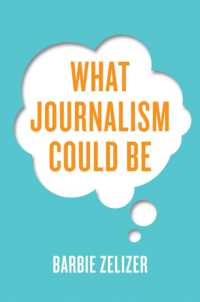出版社内容情報
軍事統制で厳しい自粛を強いられた庶民のくらしを、代用品や配給制度、隣組や学童疎開などの事項に分けて、当時の生活道具や日記、写真などの貴重な資料でみる。戦後75周年記念号。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
111
日中・太平洋戦争下に日本のくらしはどのようなものだったのか豊富な写真と解説でまとめられている。当然柄私は体験したことのないことだが当時を知る母はよく知っていた。子供心にも神国日本という言葉を植え付けられていたそうだ。教科書にも天皇崇拝が載っておりその教科書も載っていた。防空頭巾やバケツリレー、竹やりその他アメリカの空爆とその威力には到底及ぶものではなかったという。それでも日本は勝つと軍部は唱えていた。この愚かな戦争で多くの人命を失った。いつまでも心にとどめたい。図書館本2022/02/17
yomineko@💖ヴィタリにゃん💗
69
大判で資料、写真が多く心に残る本。戦争は弱い人達に特に辛い思いをさせる。出征の写真、見送る祖母らしき人の険しく悲し気な顔。やるせない。軍隊用に兎や犬猫の供出もあった。毛皮にされたらしい。やるせない。ものが極端にない中、紙製の洗面器など工夫を凝らした品々に感動。「この世界の片隅に」も載っていた。本当にこんな事があったのか目を疑う100年も前ではない日本。今はものに溢れ、食品は大量に捨てられている。この頃に思いを馳せて少しでも自分の出来る範囲で慎ましく暮らしたい。巻末の戦争資料館、出来れば全部周りたい。2022/03/06
ヒラP@ehon.gohon
22
戦争中の暮らしを思いやるにも、実感できないほどの過去形になってしまいました。2023/08/14
ちさと
18
軍事統制で厳しい自粛を強いられた庶民のくらしを、配給制度、隣組や学童疎開などの事項に分けて紹介している。戦場で戦う兵士と共に、銃後で戦う庶民がいた。戦争は戦場だけでなく、関わるすべての人を巻き込んでいく。本書で紹介されていていた「戦時下の家計簿」がわかりやすい。パンが減って芋類が増えていき、娯楽費がゼロになり、隣町会費や疎開費用が家計を圧迫し、、と少しずつ時間をかけて戦争が家計に浸透していく様、何とかしてやりくりする苦悶の日々の様子が見て取れる。「配給物絵日記」も必見。2025/05/31
hitotak
9
庶民が過ごした戦時下の毎日に、何を食べ、どういう日々を送っていたのかを豊富なビジュアル資料とともに知ることができる。食糧も乏しく、あらゆる物資が不足する中でもささやかな楽しみを探し、工夫を凝らして日常生活を送っていたことがわかる。複数の執筆者が、今のコロナ禍の日常と当時を重ね合わせる文章を書いている。災いのレベルが違いすぎるとも思うが、不安に耐えて毎日を過ごしているという部分は確かに同様だ。戦時下の日常を描いたアニメ映画『この世界の片隅に』の設定資料や、監督が語る制作エピソードなども掲載されている。2020/10/05