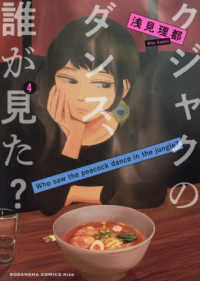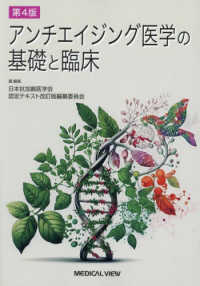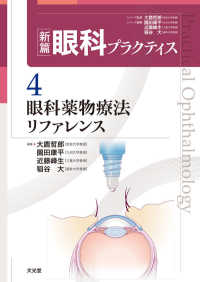出版社内容情報
SNSに投稿される「学校 いきたくない」という呟き。年々増え続ける不登校問題に、親は、学校は、社会は子供とどう向きあうべきか。気鋭の心理学者がその解決策を探る。
内容説明
2022年度の文部科学省の調査では、不登校の児童生徒数は約30万人と過去最多となった。なぜ、これほどまでに不登校は増えてしまったのか。学校の魅力の低下、個性重視の風潮、文科省の不登校に対する立場の変化など、そこには、さまざまな要因が絡み合っている。不登校の実態や背景にある心理メカニズムを探り、その理解や支援のために何が必要かを考える。
目次
第1章 学校に行きたくない、行けない子どもたち(増え続ける不登校;そもそも不登校とは ほか)
第2章 不登校にもさまざまな事情がある(不登校問題の時代的な流れ;学校に居場所がない ほか)
第3章 学校に行かないといけないのか(社会に出る前の準備期間を過ごす場;最低限必要な知識や社会性を身につける場 ほか)
第4章 自分の現状をどうとらえたらよいか(なぜ学校に行きたくないのだろうか;立ち止まって考えるのはけっして悪いことではない ほか)
第5章 周囲はどのように対応すべきか(家族の戸惑い;初期の対応について ほか)
著者等紹介
榎本博明[エノモトヒロアキ]
1955年東京生まれ。東京大学教育学部教育心理学科卒業。東京都立大学大学院心理学専攻博士課程中退。心理学博士。カリフォルニア大学客員研究員、大阪大学大学院助教授などを経て、現在、MP人間科学研究所代表、産業能率大学兼任講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
katoyann
てくてく
安藤 未空
takao
-
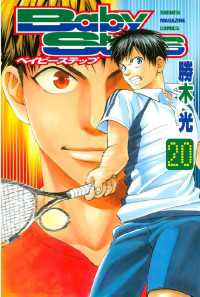
- 電子書籍
- ベイビーステップ(20)