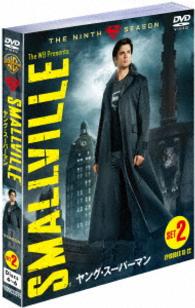出版社内容情報
他に先んじて大政奉還を唱え、幕末史における中心人物となりながらも、親藩大名という立場を変えられなかった松平春嶽の生涯を追いつつ、幕末の動向を新たな視点から構築する。
内容説明
徳川一門において、敬して遠ざけられる福井藩。第十六代藩主・松平春嶽は、藩内改革を推し進め、のち、幕政にも深く関わっていく。幕末の中心人物として、誰よりも早く大政奉還を唱え、公武一和を目指したその生涯を追いながら、幕末の動向を新たな視点で再構築する。幕府や薩長同盟とは立場を異にする、第三極の牽引者の姿を描き出す。
目次
第1章 春嶽、越前福井藩主となる―親藩大名の苦悩
第2章 大老井伊直弼との対決―安政の大獄
第3章 政事総裁職への就任と横井小楠―慶喜・春嶽政権の誕生
第4章 薩摩藩との提携路線を強める―「薩越同盟」の可能性
第5章 戊辰戦争という踏絵―新政府の主導権を奪われる
第6章 維新後の春嶽―福井藩の消滅
著者等紹介
安藤優一郎[アンドウユウイチロウ]
1965年千葉県生まれ。早稲田大学教育学部卒業、同大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。文学博士。JR東日本「大人の休日倶楽部」など生涯学習講座の講師を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
62
春嶽の評伝であるが幕末維新史としても面白い。特に安政の大獄に至る時期の井伊直弼とそれに対抗する親藩当主の動きなど、幕末史ではあまり語られない面にも詳しい。若く非常に賢い人物だったため、親藩でありながら薩長(特に薩摩)主導の維新政府側にいるというとてつもなく微妙な立場を乗り切れたことがよく分かった。物足りない面(薩長盟約により長州がイギリス製武器を購入、これが第二次長州戦争の勝因のひとつだったことなどに全く触れられていない、親友とされる山内容堂との関係があまり登場しない)もあるが、語り口も平易でお薦め。2021/09/20
きみたけ
57
以前から松平春嶽について知りたかったので丁度良い本でした。著者は歴史家で文学博士の安藤優一郎氏。安藤氏の著書では「江戸幕府の感染症対策」を読了済。松平春嶽と福井藩の動向に焦点を当て、従来の薩摩藩・長州藩・土佐藩、幕府や会津藩が主役の幕末維新史では見えてこない歴史を解き明かした一冊。結城秀康を藩祖とする福井藩は徳川宗家を継いで将軍になってもおかしくない家格であり、ある種恨み節的なバックボーンがあるようです。その背景のせいか、薩摩藩と提携路線を強めたり徳川慶喜を補佐したり、動きが分かりにくい面が垣間見えます。2023/08/14
樋口佳之
46
春嶽の歴史的役割とは、徳川一門の大名でありながら、公論をキーワードに徳川家独裁の政治体制ではなく、挙国一致の国家造りを牽引したことに尽きる。/徳川一門であった事と主張する国家像との間で葛藤した方だったか。キーマンの一人だったんだな。2021/09/15
寝落ち6段
20
御三卿・田安家に生まれ、福井藩の藩威や財政のために養子となり、藩主となった。時代は、激動の幕末。薩摩藩や長州藩、土佐藩などが語られがちだが、他の藩も重大な決断に迫られ、どう行動したのかを知ると、より理解が深まる。聡明な人物ではあるが、全てを合理的に決断するのではなく、人として何を守りたいのかというのを基準に命を差し出せるものすごく豪胆な人物だと思った。維新後も、多くの人に頼られ、その尽力の甲斐もあり、徳川の回復、旧福井藩の叙勲を目にし、この世を去った春嶽。どのような思いだったのか、偲ばれる。2022/09/12
春風
19
松平春嶽。幕末期に親藩の前藩主としては特例的に、政事総裁職として将軍後見職・一橋慶喜とともに政権運営を担った。公武一和を志向していた時期の幕府のトップである。親藩大名として“敬し遠ざけられ”ながらも愚直に政治に向き合う姿が垣間見える。左内の『誠実一筋の人柄で思いやりも深いが、乱れた世を治める器量に不足するうらみがある。天下の奸雄・豪傑を籠絡する手段を持ち合わせていない』という評が実に当を得ていた。本書は政治的駆け引きの当事者である一大名の視座から幕末史を通覧しているという点で、際立った一冊といえる。2021/09/10
-

- 和書
- 孤島論
-
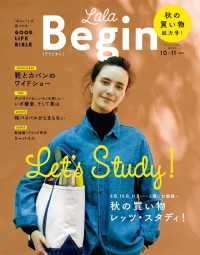
- 電子書籍
- LaLaBegin - Begin10…