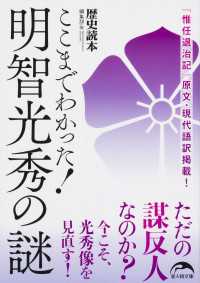出版社内容情報
文学に描かれる「橋」とは、渡るためのものではなく、人々の心を捉えるために存在するものである。小説の舞台として橋を巧みに利用することで、橋を渡る兵士たちの軍靴の足音が戦争の恐怖を伝え、橋が過去と現在をつなぐ役割を果たすことで、過ぎし日と、いまを見つめる登場人物の心の葛藤が深く投影される。
「橋」の世界が両岸を分けつなぐとき、文学はいきいきと動き出す。
内容説明
文学に描かれた「橋」とは、渡るためのものではなく、人々の心を捉えるために存在するものである。小説の舞台として巧みに利用することで、橋を渡る兵士たちの軍靴の足音が戦争の恐怖を伝え、橋が過去と現在をつなぐ役割を果たすことで、過ぎし日と、いまを見つめる登場人物の心の葛藤が深く投影される。「橋」の世界が両岸を分けつなぐとき、文学はいきいきと動き出す。
目次
1 幣舞橋を見た人々
2 隅田川の幻景
3 京都、大阪「花街」の橋
4 石橋の静かな思想
5 橋の上にある戦争
6 人生は橋を渡る
著者等紹介
磯辺勝[イソベマサル]
1944年福島県生まれ。法政大学卒業。文学座、劇団雲に研究生として所属。その後、美術雑誌『求美』、読売新聞出版局などの編集者を経て、エッセイスト、俳人に。俳号・磯辺まさる。99年第4回藍生賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
chang_ume
8
「橋」を連結点とするか、分岐点と捉えるか。著者は後者を見ているように思う。だから生まれる景色は橋の上だ。通過ではない。そこに渡る人の逡巡を見て取るか、あるいは決意を感じるか。ともに時間が橋の上で流れている。人は動かないが、川は流れる。そのコントラストも橋の条件だろうか。橋を補助線に引いたさまざまな作品紹介ですが、正直なところやや退屈でどうしたもんかなとページをめくるうち、終章で著者の熱が現れる。ただもう少し、橋への熱情(執着)が語られてもよかった気もする。はたして本書に橋は必要だったのだろうかとも。2019/10/16
てくてく
7
「橋」に関する文学アンソロジーというべきか。川端康成にとっての橋などが取り上げられており、それなりに楽しかった。2019/10/02
お抹茶
1
大阪は東京よりも水に親しく,川の水面が高い。道頓堀の橋,特に戎橋は賑わっていて,橋にかかるとほっと一息気持ちの変化を感じられる。三島由紀夫の『橋づくし』は,橋を巡る願掛けの場面場面での心理が実に細やかで,近代的な弾力のようなものを持った切れ味の良い小説。池谷信三郎『橋』の橋は,女というものの難解さを象徴している。2022/05/07



![中医臨床[電子復刻版]通巻75号](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1031221.jpg)