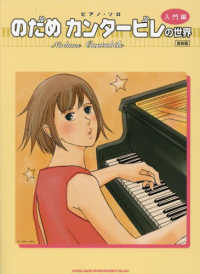出版社内容情報
奈良時代に編纂の命が出た『風土記』には各地の特産物や伝承などが記録されている。『風土記』を通して古代日本へタイムトリップ!
《目次》
はじめに
第一章 『風土記』のあらまし
『古事記』・『日本書紀』との違い
誰が何のためにつくったのか
『風土記』の種類
第二章 『風土記』の中の神や英雄たち
1 神々の群像
スサノオ神
オオクニヌシ神
ヤツカミズオミヅヌ神
カシマ大神
荒ぶる神
2 天皇とされた英雄
倭武天皇
神功皇后とその伝承
市辺天皇
第三章 五つの『風土記』の世界
『常陸国風土記』の特殊性
『播磨国風土記』と応神天皇
ほぼ完本として残る『出雲国風土記』
『肥前国風土記』・『豊後国風土記』と景行天皇の土蜘蛛征討伝承
逸文の面白さ
第四章 古代人の祈り
神社の数
寺院の数
僧と尼
神仙思想
浦島太郎のルーツ
天女と白鳥
古代人とタブー
第五章 古代の生活を支えるもの
開墾をめぐる神と人びと
さまざまな水産物
国境に住む人びと
古代人と特産物
市に集う人びと
第六章 日々の楽しみ
歌垣の実像
日々の宴会
温泉の楽しみ方
さまざまな擬音
口かみの酒
おわりに
瀧音 能之[タキオト ヨシユキ]
著・文・その他
内容説明
八世紀はじめ、国ごとに作成された『風土記』。その多くは失われてしまったが、『常陸国風土記』『播磨国風土記』『出雲国風土記』『肥前国風土記』『豊後国風土記』の五つが現存し、各地方の歴史、風俗、信仰などが記されている。古代の日本列島に生きた人びとは何を考え、どう生きていたのか?『風土記』から見えてくる、日本列島の古代史の世界。『風土記』を知ると、日本史がグンと面白くなる!!
目次
第1章 『風土記』のあらまし
第2章 『風土記』の中の神や英雄たち
第3章 五つの『風土記』の世界
第4章 古代人の祈り
第5章 古代の生活を支えるもの
第6章 日々の楽しみ
著者等紹介
瀧音能之[タキオトヨシユキ]
1953年北海道生まれ。早稲田大学文学部卒業。駒澤大学教授。早稲田大学、淑徳大学でも講師をつとめる。研究テーマは、日本古代史。特に『風土記』を基本史料とした地域史の調査を進めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かわかみ
bapaksejahtera
乱読家 護る会支持!
misui
はちめ
-
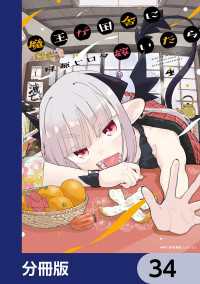
- 電子書籍
- 魔王が田舎に嫁いだら【分冊版】 34 …